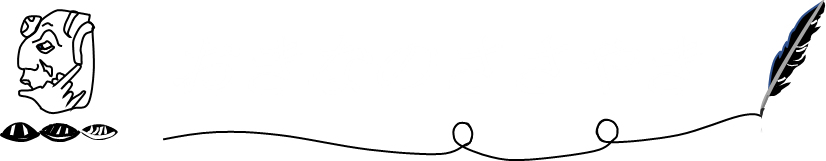~生物みな一種よりして散じて万種となる~
一虚の中より天地・日月・星宿・水火・禽獣・虫魚・草木・人類まで変化し来る者なるべし1a)
鎌田 柳泓(1754-1821)
「ある対象の概念がこの対象の現実性の根拠を含む場合には、この概念が目的と呼ばれる」とカントはいう。しかし、ぼくらが生物学において昔から議論してきた目的ないし目的論と呼ばれるものは、これとは全然ちがった意味あいをもっていたように思う。それは極めて素朴に、あるものが現実として存在するのは『なんのためか』ということにかかわるものであった。たとえば動物の目。目の目的は見るためであると言ったら、それは目的論的説明だとされた。そしてこのような目的論的説明は、科学としての生物学では避けるべきものであった。ではどう言えばよいのか?動物は目によって見る、と言うべきなのである。(略)・・今はこんな素朴な目的論争はなくなっている。(略)・・何のためにとか、目的とかいう概念は、生物学においては排除されるべきものではなくなった。むしろ、それを問わなければわれわれは生物というものを理解できない、という認識に転換したのである」(日高敏隆『目的論をめぐって』)2a)
動物は目によって見る・・・ウーム。言いえて妙である。・・・何のために。目はものを言うためだと思っていたが。なるほど、目はロック解除の目的にもなる。恵施(前320)の『目不レ見』3a), 4a)。古くて新しい問い。。そこに山があるから。
拙者‘おきな’は、進化論の歴史と数理に疎いので、学門としての進化について述べられないが、ひまつぶしに、ブログは手によって書いた(今では口でも目でも脳波でも書いてくれる+AI)。
鎌田柳泓著の「心学奥の桟」(上之巻)(1818年文政元寅のとし:1822年出版)*には、生物の進化について思案したとされる文が残されている(鎌田はカマタ、カマダとも訓む。柳泓はリュウコウともいう;鵬は諱)5a)。鵬は「北冥有魚 其名爲鯤 鯤之大 不知其幾千里也 化而爲鳥 其名爲鵬」(荘子『逍遙遊』)6a)からか5a)
*1822年出版であるが、執筆は1818年(文化13年以後、文政元年以前であるとされる)5b)と思われる。
・これを読み解くにあたり柳泓著の『理学秘訣』もあわせてみていく必要がある。また、老子・荘子、朱子学、儒学の思想が肝となる。ひとつずつみていこう。
・『心学奥の桟』 上之巻
1.天地万物は皆一針眼の虚中に其理を含蔵して出来の説
「この項、朱子学の根本思想である理―『至細の中に乃至大の理を含蔵する』―を説明するために様々な例をあげている」との注釈がある1b)。
この説を紹介する。「鶏卵は唯黄白の水なり。而して其中自微細の分別ありて、嘴距・頭足・冠尾・腸胃の所ありて各々区別せり。蓋、卵形其尖る所は嘴吻のある所なり、円大の所は腸腹・尾翼の有所なり。ゆへに化して雛となれば其形全備せり。然るに其初は唯一水の中に具足せり。されば鶏卵はおのづから鶏となり、鴨卵はおのずから鴨となり、雉卵は自ら雉となり、孔雀卵はおのづから孔雀となり、錦鶏卵はおのづから錦鷄となりて毫も相渾ずべからず。其他燕雀・鴉鷺・鷹隼の類も推してしるべし。又魚卵の如きも其初至て微細にして唯芥子の大の如くなれども、諸鱗・大小・美悪其形各々区別し、其の性情又おのおの分たり。鯨魚の大ひなるも其卵又甚だ小なり。其他昆虫・獣類又類を以て推べし。さて又土壌の如きも地によりて又各々其性品に区別有て同からず。故に其砂石・金玉・草木を生ずるに各美悪・形色の不同あり。・・(逸話:2.へ)*1・・・砂石といへども其地によりて其品各々不同ある事を。其他米栗・草木皆各々の不同ありて、地に因て其品殊なる事、しるべし、是皆其土壌に別あるゆへなり。又草木の種子の如き、梅の核の中には自ら梅の茎葉の形ありて、其仁の中に具足せり。柿の核、桃の仁の如きも皆然り。凡諸の草木みな如レ此なるべし。又烟草の種子の如きは至て微細にして、・・・されども其内に必ず烟草の茎葉一々に具足すべし。扨其成生するに至ては其茎葉の麁大なる事彼が如し。みつべし、至細の中に乃至大の理を含蔵する事を。・・・是等の理を以て推に針眼大の虚中には一切万物の理悉総具足して些も欠少なき事を思うべし。人の腎精の如きも本一箇少々粘滑の物なり。而して其一滴の内に男女・美悪・堯舜・桀紂・貧子・王公の理皆其中に具足して以て人身を生ぜり。みつべし、天理の変化、其至神至妙なる事を」1b)
《理とは?》
まず『理』について理解することが肝要である。朱子(朱熹:1130-1200)7a)によって完成した『理気二元論』は「この宇宙の間に存在する森羅万象、一切万物のあり方を、宇宙の法則・原理たる理と物質物体を形成する元素たる気との二元によって把握せんとする学説」8a)である。つまり「事物のありかたを規定する原理と、事物のあるべきありかたの法則である。理にそのありかたを規定されることによって、はじめて物は生成され、かくて事物が成立し、理に従って事物は存在し機能し運動し、人は行為する」9a)のである。朱子は『理先気後』8a)、「理を気に内在する原理として把握すると同時に、気に先行する実在」10a)としながら、一方で『理気相即』8a)「理は気がなければ存在できない。言いかえれば、気があれば必ず理がある。気が天地の間にあっては運動をしたり物を生んだり、人間にあっては思考したり喜怒したりできるのに対し、理はそうした作用とは全く無縁であり、気のはたらきに秩序を与えるものとしてそこに存在するだけである」10a)と説いている(朱子は「世界観の上からみれば気一元論であり、理は倫理学上の要請により導入」8a))。やや分かりやすくいうと、「理とは気の運行に秩序・規律あらしめる法則・原理、つまりは理法に他ならない。理は抽象的なる見えざる力であり、また理法なるが故に普遍・無限をその属性とする。つまり理は、形而下の物質世界の上に超然たる形而上的真実在」8a)である。繰り返すが、「万物の背後にそれを統括し秩序づける理法(孔・孟は天と呼び、老・荘は道と称した)があり、その理法によって万物が生み出される(一部略)」8b)のである。
理気二元論は、ギリシア哲学とも類似点があることから、理と気が形相と質料に対比させられる8a)。渡辺 徹 氏は、『理学秘訣』の解説で、「氣」は質料であり「理」は形相である5c)と述べている。しかし、ニーダムはこれについて「『理』と『氣』をプラトン=アリストテレス哲学の形相と質料に相等しいものとみなしうるという意見を、全く受け容れがたいもののように思われる。確かに形相はものの個性化の要因であって、あらゆる有機体とその目的との結合を引き起こすものであり、『理』もまたそのとおりであった。しかし、類似点はそれでおしまいである」11a)と断じている。さらに「『理』のきわだった特色は、本質的に霊魂のようなものでもなく、また、生命を持ったものではなかったという点にある。氣は理によって生み出されることはなく、理は論理的優先性を持つに過ぎなかった。理はそれ自体、実体的なものではなく、「氣」ないし「質」の何らかの形相でもなかった。理はいかなる厳密な意味においても、イディアや形相のように形而上学的なものではなく、自然界の内部の諸段階に存在する目に見えない組織化の場、あるいは力であった。純粋な形相や純粋な実在は神であったが、理・氣の世界にはいかなる『主催』者も存在しなかった(概略)」11a)と論じている。これも(解釈の)ひとつである。
ニーダムは否定するが、池田秀三 氏の言われるように「理」はプラトンの『イディア』に近いと思う(池田氏は善のイディアとしている)8a)。この世のあらゆるものが生成されるときに、そのプラン(アイディア)として導くものが理であり、それにより気は物質から形としてなすものである(物質は気から生み出される五行(質)となる)のではないだろうか(愚輩)。
さて、話を戻そう。柳泓は特に新しいことを論じているのではないことが分かる。誰もがそうだね、という話であるが、この序論が重要なのである。つまり、過去から誰もがそうだと分かっていることを、ここで述べておいて次の本題につなげるのである。
ひとつめに、至細(いたってこまか)のなかに至大の「理」を含む。理法により形を成す。卵をみると、黄身と白身があって水様である。しかし、そこには既に目や口、頭、内臓になる部分が全て含まれている(其初は唯一水の中に具足せり)。草木はどうかというと、種子が卵と同じようにその中に茎葉があり、全てを含んでいる。また、至細の中にある理に導かれ、至大のものが形成される。至細に例えている卵や種子にある理によって、至大ものである禽獣や植物となる。つまり、気によって生じる万物は理のもとに形成されていくのである。これは、先に説明した朱子学「『理』があってはじめて気が物を構成し、物が物として存在し、また物と物との関係が保たれる。つまり理に従って事物が成立し存在する」9b)の教えである。
『荘子』(知北遊)の一文を記す。「扁然として万物あり、古自り以て固く存す。六号(天地と四方)を巨と為すも未だ其の内を離れず、秋豪を小と為すも之を待ちて体を成す(天地にあまねく万物は生成し、天地開闢の以前の大昔から厳然としてそのままにあったのである。道すなわち霊妙なはたらきをもつ天地大自然の理法は、かくも偉大である。だから天地四方の宇宙空間は巨大ではあるが道を離れてその外にのがれ出ることはできず、秋の動物の毛の先はいかに細小だといっても、道の働きがあってはじめてその体を成すことができる(一部改)」4b), 12a)。
では、この時代の西欧における発生についてはどうであろう。卵あるいは種子にはそれが生体になるまでの部分(器官など)が既に含まれている ― いわゆるすべてのものは、あらかじめ神によって完成している(後述のアウグスティヌスを参照)という前成説の観点からみると、ボネ(Bonnet: 1720-1793)はアブラムシの単為生殖の現象を発見し、「すべての個体は最初から神によって作られていて、マトリョーシカのように互いに入れ子状になっており、適切なときになると外へ出てくる」13a)という説を打ち出した。雄は不要で母胎(雌のみ)からコピーの子がどんどん出てくるので、個体の基本的な形は完全に神によって定められている13a)、と思い至るのは無理もない。・・
柳泓のいう‘至細の中に乃至大の理を含蔵する’は、このボネの論やヘーゲル(1770-1831)の『自然哲学』(1805-1806草稿)にある「胚芽の発展ははじめは単なる生長であり、単なる増加である。それは即自にはすでに全植物である。諸部分はすでに完全に形成されていて、ただ一つの増大、形式的な〔同じことの〕繰返し、堅牢化〔を経る〕だけである。というのは、生成すべきものはすでに存在するのである」14a)と同じような前成説と捉えてよいのか、ゲーテ(1749-1832)の『植物生理学の予備的研究』(1790年代)に記された「われわれが有機体と名づけるものは、自分と等しいものを、それ自体に即して生み出し〔生長〕、あるいはそれ自身のなかから産み出す〔生殖〕性質をもっている。新しく生まれた同一のものは、初めはつねに有機体の一部であり、この意味では有機体のなかから現われ出るものである。これは展開説(前成説)の考えに好都合である。しかし、古いものが外界の養分を確実に摂取して一種の完全性に達してしまうことがなければ、古いものから新しいものが展開することはできない。これは後成説の概念に好都合である(概略)」15a), 15b)のような意味(前成説: preformationも後成説: epigenesisもありうる)も含んでいるのか。しかし、アリストテレスが述べる後成説16a)「一体いかにして種子〔あるいは精液〕から何か或る植物または動物が生ずるのか。・・・動物または植物の或る部分のでき上がったものが精液または種子の中に始めから内在するということも、もしすべての部分が精液または種子からできるのだとすれば、不可能である。精液はそれ自身の中に諸部分を作るものを含まない16b)。・・・まず何か或る〔一定の部分〕ができるので、すべての部分が同時にできるのではない。また、生長の原理〔栄養能力〕を含む部分が最初に生ずるのである。(これはまた自分に似た別のものを産む〔霊魂の〕生殖的部分でもある)。心臓のある動物ではこれが、その他のものでは心臓に相当するものが、発生の原理〔始まり〕なのである16c)(概略)」を意味しているのではないことは明らかのようだ。現代では後成説が支持されているが、遺伝情報を考えると前成説でもあり、その後の生育における変化は後成説でもあり、ゲーテが言うようにどちらともいえない。柳泓の『理』の概念は変化を受容するものであるが、少なくとも、この時代に柳泓はアリストテレス、あるいはWolff(ヴォルフ)が『Theoria Generationis』(発生論:1759)で唱えた後成説15b)「In Bezug auf die Gesetze oder die Art der Bildung stimmen wir ohne Zweifel Alle mit Aristoteles überein, dass dieselbe nämlich durch allmähliche Hinzufügung von Materie geschieht oder durch das Zusammenkommen von Theilchen.17a):法則や形成方法に関しては、私たちは間違いなくアリストテレスに同意する。すなわち、それは物質が徐々に追加されることによって、または粒子が一緒になることによって起こる†」を知っていたとは思われない。
ふたつめに、種(類)の維持、すなわち自己複製を説いている。鶏卵からは鶏が、鴨卵からは鴨、孔雀卵は孔雀になる。別のもの(類)になることはない(少しも混じることはない)。他の生物、魚、昆虫もそうだ。同類、同種を生み出すことについて、『荘子』(知北遊)の「萬物以レ形相生」4c), 12b)は「万物は(その種族の)形を(再生産して)生じていく」18a)とも解釈されうる。それは当然ながら、生まれてくるものが次から次へと別のものに変化したら世の中はカオスとなる。このように、万物にはすべてに理が具わり、ある生物はその生物を生み複製を続けることを説く。
みっつめに、理法によって同じ種から同じ種が生まれ出ることを述べているだけではなく、気の変化によるものの分化があることも述べている。ある種類から生まれた卵・種子には理が存在してその種類を成体となすが、その種類には様々な異なるもの(変異)が見られる。〈砂石といえども其品各々不同あること、米栗・草木皆各々の不同あり〉と。さらにいうと、その類の起源をも示唆している〈魚卵の如きも其初至て微細にして芥子の大きさの如くなれども、その形各々区別し、其性情又おのおの分たり〉。つまり、逆に言うと、様々な類に分かれた元は、見ためには同じ卵であった、という起源につながっている。
さて、‛至細の中に乃至大の理を含蔵する’は、西欧における発生の意味を柳泓が理解しているのではないと言えるが、気になる点がある。柳泓は発生を理=神として思案しているのか?本説の結びに、〈天理の変化、其至神至妙なる事〉とあるように、(天)理は神的なもの、妙(霊妙)なるものとして捉えているのであれば、理によって定められたもの、つまり神によって定められたものとして西欧の前成説と同じ論を踏襲しているよにもみえる。しかし、そうではない。決定的に異なるのは、‘みっつめ’に記した『変化』である。
本来、『天理』とは、「朱子学では、人間の持つ五常(仁義礼智信)」19)をいい、「天理に従う行為を人に求めるところにおいて、天と人とが合一することとなる。万物に賦与された理こそが天命である」19)ようだ。あるいは、「今の学ぶものは、学問をする要を知らない。それはただ、この道理が天理に他ならないことを窮めることだ。天理は天地の間に存在している(林恪)」10b)、「天理はもともと多くて、人欲というのも天理のなかから出て来たもの(黄榦)」10c)ともあり、柳泓は万物に賦与された理は定められたものではあるが、人間をみると、男女・美悪・堯舜・桀紂・貧子・王公のように、‛各々不同’でもある。つまり、一滴の内には初原なる定められた理が存在するが、それは多様性を含むものである。柳泓は前成説をうたいながらも、そこには偶然性とともに行く末の分化があることをも示し、『天理の変化』と結んだのである。 †‛おきな’訳
2.鉱物は生命の起源か?
面白いことに、柳泓は無生物の砂石(鉱物)についても取り上げて考察している。鉱物を自然からの生成物、魂と繋がるものとして捉え、動植物と同じく、土地によって産出される石が異なっている、裏を返せば同じ土地から同じ石が産出されることを思案したのである。『理学秘訣』の「問、玉石金鉄ハ何ニ物ゾヤ。曰、石ハ地気ノ久ウシテ凝ツテ堅剛ヲ成ス者、金銀銅鉄ハ皆石ノ精髄ニシテ、其石ノ品殊ナルニ因リテ、其質各同ジカラザルノミ。玉及ビ水晶・瑪瑙ノ類ハ、皆石ノ精キ者ニシテ、其質稍異ナルノミ。蓋シ此一類ハ、士気ニ水気ヲ含ンデ生ズル者也。故ニ皆光明透徹セリ」1c)と書いている。
かつて鉱物は神の創造物としてリンネ『自然の体系』では三界として動物界・植物界・鉱物界に分類20)されていた。鉱物というと、動植物とは異なる非生命体でまったくの別物、と今では奇異に感じるが、古くから石も成長する(生きている)と考えられていたことによる21a)。神話の世界や伝説などでも見られるように、石にも命(魂)が宿っているのである。
石から子供が生まれるギリシア神話21b)、日本では『日本霊異記』(日本国現報善悪霊異記:810-824頃)に石を産んだ女、石から生まれた女の話がある21b)。あるいはタレスの「万物は神々に充ちている」22a)(磁石のような不思議な力からなどから洞察したと考えられている)22b), 23a)という物活論もそうである。拙者は、ディオスコリデスの鉱石で述べられる‛石の薬効という力’24)よりも石に埋め込まれた生物の姿を見て石にも魂(命あるいは神)が宿り、石から生物が生まれたという神話、伝説、哲学が作られたと推測するのだが。驚くことに、クセノファネス(前570頃~前470頃)はこれを化石と見破っている25a)。
今でも、宝石類、パワーストーン、あるいは落ちている石にさえ、なんらかの力、霊的なもの、命が宿っているように思う人も少なからずいる(多いか)。さざれ石(岩はさざれ石が成長して大きくなったもの)21a)もその例か。石門心学は「儒教的思想を基調としながら、部分的には仏教や神道の諸観念をも混じている」1d)(柳泓は儒・釈・道を三教一致とした)5d)であることから、神道のいわゆる「神々は自然の中に宿る」26a)(森羅万象に神が宿る)という思想を具えていることは自然である。なお道家においては、ニーダムは「自然の中で起こるかもしれない驚くべき変形の概念を、他の、より空想的なしかも根拠のあまり十分にない例証に拡大した。・・いったん根源的変形というこの確信が確立されるようになると、それから緩慢な進化的変化―それによってある種の動物や植物が他のそれから生ずるという―の信念までは、たいして隔たりではなかったのである」18b)と述べ、この変形の概念は『淮南子』の「地中の鉱物や金属の継続的変化による緩慢な成長と発生へも適用された。・・・(無機的世界へも及んだ)」18b)としている。
『淮南子』(墬形訓)より「正土(中央の地域:主要な土地)の気は、埃天(中天)を統御する。埃天は五百年で缺(黄玦:鶏冠石?:ヒ素の硫化鉱物)を生み、缺(玦)は五百年で[黃埃を生み,黃埃は五百年で]**黄澒(澒:水銀)を生み、黄澒は五百年で黄金を生み、黄金は千年で黄龍を生み、黄龍は地に蔵れて黄泉を生んだ。黄泉の埃が天に上って黄雲となると、陰陽の気が衝突して雷となり、激揚して稲妻となった。上のもの(水)が(雨となって)下に流れていき、流水となって通じ、黄海で合流する」27a), 28a)と、気から鉱物が生まれ、生物への変転、そして自然への回帰を記している。 **原本に記載あり
ちなみに、生命の発生で議論されている説として『鉄イオウワールド仮説』があり、「硫化鉄などの鉱物が化学進化を推進し、それによって生じた生体分子が初期生命の誕生に寄与したとする」29a)説で「現生の生物がもつ鉄イオウタンパク質は初期生命の代謝系の痕跡を保持しており、非常に古いタンパク質群であることが示唆されている」29b)のである。これに関して、『鉱物を触媒として、水と二酸化炭素から有機物が合成できる』30), 31)という、驚きの報告があった。つまり、有機物は鉱物の触媒でつくることができる。すなわち、鉱物を介して様々なアミノ酸(タンパク質)やRNA、DNAを生み出してきた可能性がある。いわずもがな、生物と鉱物は無縁ではないことは分かる。鉱物が生命の源であるとすれば、頭の中をリセットする必要がある。
*1の逸話をここに記す。
「昔城州山科郷の馬夫(むまかた)其駄する所の貴族の金箱を開きて金子を偸取、其跡へ河原の石を入かへ置ぬ。已に東都(ゑど)に至りて後、箱を開きみれば石なり。されば五十三駅(つぎ)の中、何れの馬夫の所為(しわざ)なりや知がたかりしに、一智人(ひとつのかしこきひと)有て吏(やくにん)をして五十三駅づゝの石を取よせて比べ見しに、山科郷の石に相違なければ、其地の馬夫を捕て吟味せしに、果して其実を得たりとなん。みつべし、砂石といへども其地によりて其品各々不同ある事を」1e)(ある馬夫が旅中の貴族の金箱から金子を盗み、その金箱に石を入れた。貴族が気づいたのは江戸についたときであった。しかし、知恵者が五十三駅(宿場)から石を取り寄せて見比べて同じ石の産地である駅の馬夫を捕らえた)という。動物、植物と同じように無生物の砂石にも種類があり、土壌も地域によって異なっている。即ち、その地ごとに異なったものが生み出されているのである。
この逸話の前文には〈土壌の如きも地によりて又各々其性品に区別有て同からず。故に其砂石・金玉・草木を生ずるに各美悪・形色の不同あり〉とあり、その後に〈砂石といへども其地によりて其品各々不同ある事を。其他米栗・草木皆各々の不同ありて、地に因て其品殊なる事、しるべし、是皆其土壌に別あるゆへなり〉と記され、柳泓は環境条件の中で、土壌(土)が物の変異を生んでいる要因として考えているのである。土壌は地によって異なり、石のみでなく、そこに生えてくる植物の品(種類、品種、品質など)も違ってくる、と。思うに、『淮南子』の「土地各以其類生(土地は各々其の類を以て生ず:土地は各々其の地に類似したものを産出する)」28b)から草稿につながった可能性もある。
そこで、である。次の主題につながる。
3.一種の草木変じて千草万木となり一種の禽獣虫魚変じて千万種の禽獣虫魚となるの説1f)
<環境による変化を主張しており、進化論・遺伝学の考え方に近づいている>1g)と書では解説されている。全文を記す。
「松樹に数品あり、女松・男松・五葉・一葉、又白松とて葉みな白き者稀にあり。又蝦夷松は其葉杉に類せりとかや。蓋、寒国ゆへ左ありとなり。さて又同じ松にても其形状地に由て各々易あり。京師橐駝家なんどにいへる河内松・山科松なんどの如き是なり。蓋、其はじめは唯一種の松樹なり。土地の異なるによりて変化して種々の形状をなすのみ。これをもつて推に杉槇なんどの類、凡其葉細長なる者はみな松樹より変化し出だせるなるべし。夫よりまた一変して長短方円の枝葉を変化し出せるなるべし。猶近年浪華の地に牽牛花を賞するによりて種々の花葉を変出し蔓延して数百種となり、其形状千態なるが如し。見つべし、是を以て推に凡天下に所有千草万木みな一種の植物より変化し出せりといふとも可なり。又有情の類、禽獣・魚鼈・昆虫の類もみな異類互に相交接して無量の形状・性情を変化し出し来るなるべし。たとへば唐犬を和犬と交感すれば必ず半犬を生ずるが如し。これを以てみれば天下の生物有情非情ともにみな一種よりして散じて万種となる者なるべし。人身の如きも其初唯禽獣胎中より展転変化して生じ来るものなるべし。但、人は万物の中にて最貴きものなれば其生ずる事、最後にあるべし。猶又其至りを論ぜば唯一虚の中より天地・日月・星宿・水火・禽獣・虫魚・草木・人類まで変化し来る者なるべし。但、大虚は一気にして天地の間に有て最精き者なり。俗人大虚を以て無物なりと思へるは皆深く考へざるゆへなり。魚は水中に有りて水をみず、反て大虚をみて以て有物とせり。人亦気中に有て気をみず、反て水を見る。その理同一なり。能々心を潜て考ふべし」1f)(下線は加筆。禽獣:とりけもの、魚鼈:うをすつぽん)
これをどう解釈するかである。まず、同じ類のものでもいろいろあることは、先に記した。これが基本である。
最初のフレーズの松について。まず、松の中にも樹の形状、皮色、葉などが異なるものがある、と思案している。松といっても、女松・男松・五葉・一葉(いずれもマツ科:Pinaceaeのマツ属:Pinus)32a), 33)といろいろな姿(形状)、樹皮(肌)の色、葉の形や色がある。〈白松とて葉みな白き者稀にあり〉とは、白松(Pinus bungeana)34)の樹皮は白いが葉はふつう白くない。が、この書にあるようにまれに葉の白いものがあるようだ。拙者は、白い松というと、[もなか]を思い浮かべてしまうのだが。なお、女(雌)松はアカマツ(P. densiflora)、男(雄)松はクロマツ(P. thunbergii)である。また、一葉のクロマツは一葉松33)(一つ葉松)という。このように、今でいうところの属(genus)の中にも様々な種(species)があること、同じであるものが変化して存在しているのではないか、すなわちもとは同じではないか、と。
《蝦夷松の葉は杉に似ている。これは、寒い地方であるからであろう。さて、同じ種類の松でもそれが生育している地で形状が違う。其はじめは唯一種の松樹なり。土地の異なるによりて変化して種々の形状をなすのみ。杉や槇などの葉の細長いものは、みな松の樹より変化してきた。また長短、角や丸の枝葉への変化もした》。これについては、まず、スギとマツは別の植物であることを前提として話がされている。ここで、蝦夷(北海道)の地に生育しているエゾマツの葉は異なる植物であるスギという葉に類似していると考察している。このエゾマツの形態変化について、ひとつには『蝦夷』という地理的な隔離があること、また《寒い地方であるから》という本州とは異なる環境条件(特に温度条件)による、適応あるいは選択が生じたことを推察している。
また、同じ種類の河内松と山科松をあげて、〈その地で形状が違う〉、いわゆる生育する環境条件(土壌、気候)によってその形は変わりうることをみている。これが一代限りの変異でなければ、より狭い範囲で生じている変異として捉えている。これは、生育する段階での、例えば気温の変化で葉の色が濃くなる、花が多く咲く、枝が増えるなどという一時的な形質発現への影響ではなくて、次世代に繋がる遺伝子の変異を伴う変化、つまり、種というのは金太郎飴(cookie-cutter)のような画一的に決定されたものではなく、多様な形質を生むことを提言している。
松の形態変化について〈寒い地方であるから〉、〈土地の異なることによって〉という。この文章からは、種の変化はその地の環境条件が影響を及ぼしている、すなわち環境にあわせるように変化した(環境への適応)、とも読める。しかし、蛇足ながら『自然選択説』は、環境が生物に変化を及ぼしてその地に適したものができたのではなく、出現してきた多様なもののなかからその地の条件に適しているものが選択された、と考えるべきなのである。もしや柳泓はマツの多様性を適応放散35a)のような例とみなし、〈単一の祖先種〉から形態・生態的に多様の子孫種が形成され、それぞれの地域の自然条件(山・川、地形など)によって隔離された集団は、その生息地の環境に適応した、ゆえに種々の形状をなしている、と思案したのか?
最後に、〈これをもつて推に杉槇なんどの類、凡其葉細長なる者はみな松樹より変化し出だせるなるべし。夫よりまた一変して長短方円の枝葉を変化し出せるなるべし〉と結んでいる。縁遠いと思われる杉や槇も葉の細長い特徴から松が変化したもので、逆に短く丸い葉にも変化しうるともいう。はじめは一種のマツであったが、多くの種類があるのは形態が変化したからである。その形態は環境条件によって変化しうる。従ってスギやマキの葉が松に似ているのはマツから変化してきたからである、類似の葉をもつものはマツ由来である。さらに飛躍した考察を行い、形態の変化は一定の方向に生じるのではなく、葉は長くも短くもなる、すなわち、どのような方向にも変化し生み出しうるという、朱子學のいわゆる万物化生の思想であるが、ここに《起源はただ一種である》ことを明言している。
ところで、杉や槇までも松からの起源としているが誤りである。樹木の種の分類は今後も変わるかもしれないが、蝦夷松(エゾマツ)はマツ属(Pinus)ではなくトウヒ属(Picea)32a)に分類される。杉はスギ科スギ属で日本の固有種とされてきたが、現在はヒノキ科(Cupressaceae)のスギ属(Cryptomeria)36), 37)に分類され、松とは別に分かれてきたようだ37)。同様に松とは別に分かれた槇は、イヌマキ(マキ科(Podocarpaceae)イヌマキ属(Podocarpus))32a), 37), 38a)、あるいは葉がより細長いヒノキ科のコウヤマキ(コウヤマキ属:Sciadopitys)32a), 37)とも思われるが不明である。杉も槇も松から直接分化してきたのではないが、その類似性の着眼により松樹(常緑針葉樹、マツ綱:Pinopsida37))から変化し出でるという推測は、当たらずとも遠からずというところか(結構、遠縁である)。大事なのは、ひとつの起源なるものから分化が生じたということだ。
余談だが、杉も槇も『日本書紀』には「素盞嗚尊が身体の各部分の毛から、杉、檜、柀、櫲樟の4樹種をつくり、杉と櫲樟は船材、檜は建築材、柀は棺材に定めた」38b)とあることから、我国の代表的な樹木でもあった。
松を例にあげたのは、身近で種類が多く知られていて、分かりやすい例えである。『おそ松くん』の6人兄弟(六つ子)を思い浮かべると納得する。しかし、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松の中で、カラマツはカラマツ属(Larix)32a)、トドマツはモミ属(Abies)32a)である。当然、その他は松にはない。ちなみに、五葉松は盆栽で育てやすいと言われて育てたが枯れてしまった。何がよくなかったのか。お粗末。
4.アサガオで「種」の分化と起源が分かった
何か思ふ 何かは嘆く 世中は たた槿の花のうへ之つゆ39)
なにかおもふ なにかはなけく よのなかは たたあさかほの はなのうへのつゆ
清水観音と伝えられる。朝顔は『槿』と書かれた。‛なにとかなけく’となっているのもある40)。誤記か。
鎌田柳泓は、《アサガオを賞するによりて種々の花や葉の違うものを作出して数百種となり、その形状は千ほどにもなった。これから推測するにこの世の草や木は、みな一種の植物より変化したものということもできる》と大胆にも宣言している。
アサガオ(Ipomoea nil:英名Japanese morning glory)41a), 42a)は日本が誇る花卉で、江戸末期の文化・文政(1804-30)の頃が栽培の最盛期で品種改良も盛んに行われ42b)、世界の園芸でも類をみない独特の品種を生み出してきた。もはやアサガオではない葉の形状や花の色・形を創出している。アサガオなのにヒルガオ科でありサツマイモ属43)(かつてアサガオ属(Pharbitisはシノニム))42a)であるのもなんとなく違和感をおぼえるが。このアサガオの遺伝的な大きな変異がおそらく、鎌田柳泓の発想に大きな影響を与えたのは疑いない。
園芸植物大事典をみると、「水野元勝『花壇綱目』(1664)では青と白の2色にとどまるが、平賀源内『物類品隲』(1763)に「花色数十種・・・。重弁のものあり奇品なり不結実・・・」として、変化アサガオを明記している(一部略)」42c)とある。その40~50年後、文化文政期には変化アサガオを中心に大阪で大流行42c)となっている。柳泓が『心学奥の桟』を著す直近の1814年に峰岸正吉『牽牛品類図考』をはじめ、四時庵形影『あさかほ叢(朝顔叢)』(1817)など多数の図譜入りの書が出回っていた42c)。また、秋水茶寮痩菊『牽牛花水鏡(前編:後編は不明)』(1818)(牽牛品水鏡42c)は誤記)には変化アサガオの採種法や変化咲の見分け方などが書かれている42c)(原文と現代訳の対比の書がある)41b)。

当然ながら、京都に住んでいる柳泓はこの熱狂に巻き込まれ、変化アサガオを否応なく見ており、書物も、またそのわざも知っていた。これは驚きであったはずだ。どう見たって朝顔にみえない(図―1参照:作出年は不明)。アサガオという一なるものから、妖怪変化のようにこれまでにない姿・形のものが生み出されていく。しかも、もとをたどれば一なるものに行き着く。このアサガオの多様な品種が、‘種の起源と分化’の発想のセレンディピティになったのだ。
変化アサガオの品種作り技術は世界の先端
―メンデルより先に遺伝の分離、独立遺伝を観察で知り、技術を編み出していた―
シーボルトが「この極東の島国における応用植物学、すなわち栽培や育種の研究は、ヨーロッパのどの国よりも進んでいる」(1829年ドイツの学会に書き送った報告)44a)と驚いたアサガオの品種開発をみてみよう。株(植物個体)の性質によって、親木(おやき)、出物(でもの)、正木(まさき)の区別がある45a)
親木は種子を産むもので、その子孫も将来にわたって種子を生み出せるものを言う。つまり、雌側の植物として用いられる(実を結んで種子を得るための維持用)45a)。また、出物(変化朝顔の多くで種ができない)の兄弟株を指す。出物の兄弟株の中で普通に見える株から種を取って維持をする45b), 46a)。遺伝学的には潜性*突然変異のヘテロ接合株である46a)。
注*)現在、劣性は【潜性】、優性は【顕性】を用いている。
出物とは、親木の種子から分離してくる不稔の鑑賞用株または系統46a)。遺伝学的には不稔の潜性突然変異のホモ接合株46a)。「親木より出てきたもので、親の形質には似ていない観賞上の目的となる植物体をいう(花や葉が観賞の目的となる。種子を得ることは目的としない)。親木から出てきた子は次の親木になるものもあるが、これ以外は出物である。しかし、出物でも種類によっては結実する。例えば、牡丹咲の出物は牡丹咲になるが結実せず、獅子八重の種は出物でも実を結ぶ(一部改)」45b)とある。別の言い方をすれば、出物とは変化朝顔であり、この多くは採種できない(不稔)。これは、変化アサガオは雄ずいや雌ずいが弁化する(花被⦅花弁や萼片⦆になる)ために、普通は実は結ばない。
出物でも種類によっては結実する45b)とあるが、八重咲は雄しべの葯が花弁になっただけで、稔性がある47a)(雌しべは正常なので種子がとれる)。この八重咲からトランスポゾンの転移によって雌しべも弁化し、不稔となった牡丹咲ができたと考えられている47a)(牡丹咲は雌ずい・雄ずいがないものをいう45c);牡丹咲きでは雌ずいが花弁と萼(状)からなる花の繰り返し構造となる47a), 48a))。一方、獅子咲(花弁が裂けて花弁の表裏に小さい花びらが付着するもの、しばしば花筒に袴という付属弁が付くものがある。また花弁の先が風鈴のような形になるのもある45d), 46b))では牡丹咲とは異なり、稔性のある(雄しべ、雌しべが弁化していない)単純な変異が生じて獅子咲となり、それが維持されてきた。そこから獅子咲のさらなる変異形(雄ずい、雌ずいの弁化したものは獅子牡丹という)49)を得てきている47a)。このような違いが遺伝子レベルで分かったことは感慨深い。江戸時代に経験と観察によって得た知識と技術が、現代の科学によって理論づけられて説明できるようになろうとは。
「奇花を翌年出現させるために、まいた種の中から、外見的には普通咲きのアサガオ(対立する遺伝子が異なる)から採種して、その種をまいて、そこから出てくるわずかな「出物」(子葉の異形で分かる)を選出する(一部改)」42c)。いいかえると、「変化アサガオの種子が得られない場合には、親木の種子をまけばよい。つまり、変化アサガオ(例:aabb)の雄しべや雌しべが花弁状になって種子ができないときは、まいた中で普通の丸咲個体(AaBb)から種子を採ってまけということである。遺伝学的には、表現型は正常で、遺伝子型が潜性注)ヘテロものから採種せよ(一部改)」48b)とある。親木から牡丹出物ができる仕組みは『変化朝顔図鑑』46c)や『伝統の朝顔Ⅱ』41c)に分かりやすく図示されている。また、子葉の特徴が葉や花に現われる形質と結びついているものも多くある46d)。仁田坂 氏は変化朝顔の研究から「江戸の愛好家たちは、複数の変異を隠し持つ親木から、さまざまな変異の組み合わせが生まれることを観察し、遺伝形質が分離可能なものの組み合わせであり、独立に因子のような形で伝わることを知っていたのだろう(一部改)」50)と感嘆している。
正木とは、「それ自身にて観賞上の美質と結実用の機能とを有するものにて車咲の如き多くは之れなり」45e)とある。変化朝顔のうち、稔性のある(種がとれる)系統である46a)。桔梗咲き、木立ち、枝垂れ、台咲き、縮み咲きなどあり42b)、基本的に後代もその形状・色などは分離しない。
普通、このアサガオの多様性(変異)と共通性(類似性・同一性)をみて他の植物にも当てはまるのではないか?と思いつくことはそれほど困難ではない。柳泓は、このアサガオの事象、出来事にピーンときて、マツ(松)も思案したのではないかと推測する。多様な松ももとは同じであったのではないか?と。しかし、違う。さらに深く洞察した。このアサガオの品種開発をみていると、もととは異なった形質の個体が現れ、その後も子孫を得て独立した系(系統)、いわゆる変種(ここでは品種)となっていく。しかし、交雑されたものの中には、生殖のメカニズムにより後代(次世代)が得られないものが出てくる(接合後隔離)。これはその世代で消えていく運命にある。すなわち淘汰される。一方、残されていくのは、人為による選択である。もし、自然がこれを行ったら、…そう、松のように、寒い地方(環境)に適した種だけが残るのではないか。いわゆる自然選択の作用である。
【同じもの(種)を維持するための適応と選択がある。また、子孫を残して変化していくことのできるもの(新種)、すなわち変化した中で①自然条件に適応(適合)して生き残れるもの、②生殖不適合(生殖的な隔離:接合後の隔離)により消えゆくもの、の淘汰を見抜いたのである。遡ればすべての植物はこのように一なるものより多となったのだ】と(残念ながらこのようなことは書かれていない)。
西欧においては、植物は動物と違って雄雌がないと思われてきた。紀元前にナツメヤシの雄花をもった交配の絵が描かれているのに(バビロニア.700B.C.頃)51a)、アリストテレスは、植物は雄雌の能力が混じっていて、雌と雄とに分かれていないと考えていた16d)。確かに、動物のように雄雌が分かれていないという意味では、同一の花の中に雄雌がある両性(全)花や、雌と雄が分かれていない雌雄同株も多いので気がつかなかった、のかもしれない。わが国においては、江戸末期においても雄ずい(葯:花粉)と雌ずい(子房:卵)の機能の理解ができておらず、花粉の役割を正確に理解していなかったようである48c)。しかし、本当にアサガオの園芸家が知らなかったのか疑念が残るので、西欧の事情を以下に記す。
カメラリウス(Camerarius)のコペルニクス的転回
植物の有性生殖を発見したのはカメラリウスである52)。残念なことに、メンデルは知っていてもカメラリウス(1665-1721)を知っている人はほとんどいない。先に、1676年Grewは雄しべは雄の器官で花粉は精子の役目がある事を述べている53)。その後、1694年カメラリウスは【植物に性別があることを明らかにした】。要するに、動物と同じように雄雌があり、その機能があるということである。「So gehts mit vielen Pflanzen, bei denen die Fruchtknoten erst entstehen, die dann berührt Vom Blüthenstaub anschwellen, und im Innern den Keim einer Pflanze bergen. ・・・Bestätigt seh’n wir jetzt mit Verwunderung Für Thier’ und Pflanzen gleiche Geschlechtlichkeit! Was lebt, was Nachkommen hervorbringt, Alles entsteht auf dieselbe Weise.54a): 多くの植物において、まず子房が発達し、その子房が花粉によって膨らみ、その中に胚が含まれている。私たちは驚くことに植物も動物と同じく性があることを知った!生きているもの、子孫を残すものは、すべてが同じように誕生する†」これは人類史において大発見であり特筆すべきことである。また、種の異なる交雑を行ってその可能性もみている54b)。そして「O hehre Allmacht, die Du die Welt erschufst, Du sorgst die Ordnung, welche Du eingesetzt, In der Natur stets zu erhalten, Liebst zu verjüngen die alte Schöpfung.54a): 尊き全能よ、世界を創造されたあなたは、自然界に築かれた秩序を常に維持され、古い創造物を生まれ変わらせることを望まれる†」と締めくくっている。
早くもカメラリウスの報告を(おそらく)念頭にライプニッツ(1646-1716)は「植物には、種子つまり動物で卵に相当する配偶子以外に、雄の名に相当する別の配偶子があるという推測、言い換えればそれは粉(花粉:pollen)であり、ばらまかれて雌の配偶子(卵)と結び付く・・・(一部改)」(人間知性新論:1703完成)55a)という考察を行っている。[qu’il y a dans la plante, outre la graine ou la semence connue qui répond à l’œuf de l’animal, une autre semence qui meritocratic le nom de masculine, c’est-à-dire une poudre (pollen,…) que le vent ou d’autres accidents ordinaires répandent pour la joindre à la graine qui vient quelquefois d’une même plante et quelquefois encore d’une autre voisine de la même espèce,…]56a)。この植物の雌雄性については、必ずしもすぐに肯定されるものではなかったようだ52)。しかし、ヴォルフ(Wolff)は1759年に植物の胚形成は花粉を雌しべに付けることによって生じること(Befruchtung : 受精)を明記している。[Der Embryo der neuen Pflanze entsteht also insoweit aus dem Anlegen des Pollens an das Pistill, als der Pollen eine vollkommene Nahrung ist. Nun bezeichnen wir, wenn wir erfahren, dass nach dem Anlegen des Pollens an das Pistill und die in ihm enthaltenen Theile auf irgend eine Art der Embryo einer neuen Pflanze entstehe, diesen Vorgang, insofern er dieses lestet, als Befruchtung, den Pollen aber, insofern er daran betheiligt ist, als männlichen Samen.]17b)。
種間の交雑においては、Fairchildが1717年以前に行ったナデシコとカーネーションの交雑53)、あるいは1760年にはKölreuter(ケールロイター:1733-1806)はタバコを材料として種間雑種を得ている。また同時に種間雑種は不稔となることも見ており51a)、植物育種においては交雑によって親と形質の異なる子が現れること、子ができないことも明らかにされた(すでに動物では、アリストテレスの時代にロバとウマの子(半ロバ)の「ラバ」と「ケッティ」の区別はしていないが、「半ロバ」は基本的に生殖不能ということを知っていた)16e)。ただ間違いなく、この植物による交雑の試験結果は進化思想に大きな影響を与えたことは確かであり、進化思想の引き金となったことは疑いない57a)。その端緒はカメラリウスの発見にある。
エラズマス・ダーウィンの『Zoonomia』(1794)にKoelreuterが『自然の種が他の種に完全に変態する』と呼ぶ58a)、受粉によって種が改良される内容として、「植物の雌としてタバコのNicotiana rusticaの柱頭に別種のN. paniculataの花粉を付けて、その種子を得て、その種子から出た雌しべにN. paniculataの花粉を交雑すること(戻し交雑)を何世代も繰り返すと、雌(N. rustica)の植物は雄の種(N. paniculata)に近づき、雄と同じような植物体を得ることができた†(要約):M. Koelreuter impregnated a stigma of the nicotiana rustica with the farina of the nicotiana paniculata, and obtained prolific seeds from it. With the plants which sprung from these seeds, he repeated the experiment, impregnating them with the farina of the nicotiana paniculata. As the mule plants which he thus produced were prolific, he continued to impregnate them for many generations with the farina of the nicotiana paniculata, and they became more and more like the male parent, till he at length obtained six plants in every respect perfectly similar to the nicotiana paniculate; and in no respect resembling their female parent the nicotiana rustica. Blumenbach on Generation. 58a)(farina: pollen)」ことが紹介されており、植物の交雑育種はかなり知れ渡っていたと考えられる。ついでながら、同時期にゲーテの『植物の変態を説明しようとする試み』(1790)15c)において生殖器官としての《雄蕊》と《雌蕊》が解説され、「花粉は雌性器官を求め、雌蕊にまつわりつき、その影響を与える。花粉内の液が雌蕊によって吸いとられ、受精がひき起こされる、との意見に賛成しないわけにはいかない(要約)15d):Die feine Materie, welche sich in den Antheren entwickelt, erscheint uns als ein Staub; diese Staubkügelchen sind aber nur Gefäße, worin höchst feiner Saft aufbewahrt ist. Wir pflichten daher der Meinung derjenigen bei, welche behaupten, daß dieser Saft von den Pistillen, an denen sich die Staubkügelchen anhängen, eingesogen und so die Befruchtung bewirkt werde.59a)」とあるように、まだ受精のメカニズムは解明されていないものの植物の性の理解は深まっていた。
江戸のアサガオの変種の作出において、交雑についての記録は残されていないが(門外不出としてか?)、蘭学として雌雄の知識は伝わっていたとされ48c)、おそらくは誰かはこのような情報を聞き知っていたのではないか、あるいはこのことは知らなくても交雑(交配)を行っていた、とも想像する。 †‛おきな’訳
では、動物は?その前に雑談を。
5.雑談
江戸時代には園芸としての花を愛でる文化が庶民にも広がり、オランダのチューリップ熱と同じくして「ツバキ、それも変わり種のツバキの栽培熱からはじまった。・・・元和・寛永(1615-1644)の頃になって爆発的に愛好熱が高まった(一部略)」60a)ようだ。また、菊も人気があり、花の変異も朝顔に劣らず大きいものがあるが、長くなりそうなので割愛する(キク科にはヒマワリ、レタス、ゴボウもある)。小学校ではアサガオとヒマワリを栽培することが多い、と思う。アサガオは無限伸長性のつる性植物で腋芽(脇芽)から花を咲かせながら成長が続く。一方、ヒマワリは有限伸長性の植物で主茎が花で止まる頭花である。このふたつは植物の形態を代表すると昔の先生は教えてくれた。
ついでに花菖蒲(ハナショウブ)も
はなびらの 垂れて静かや 花菖蒲(高浜虚子)
ハナショウブ(アヤメ科アヤメ属)32b)は、ショウブ(ショウブ科ショウブ属)32c)とは全く別の植物である61a)。花菖蒲は江戸時代になって栽培が盛んとなり、江戸の後期には多くの品種がつくられている61b)。松平左金吾(1773~1856)は蒐集した花菖蒲を用いて形態、色の異なる約200品種を作出した61b)。花形の変わった変化咲の‘玉宝蓮’、‘白天女’、‘五三の宝’など62a)があるが、さすがに花や葉の基本形から花菖蒲と見分けがつかないような変異はほとんどみられない。しかし、これももとなるものから異なる種類のものを生み出せることを示している。花菖蒲の品種改良は江戸が中心であったことから、柳泓にとっては朝顔の方が身近であったと思われる。
バルブバブル、チューリップ
オランダでは1630年代にチューリップバブルがあった63a)。チャンセラーの『バブルの歴史』63)をみてみよう。「チューリップの品種を花の色で分類し、軍国の階級からとった名がつけられ、富の象徴とされた。ある品種の球根(bulb)1個は家が買える値段以上にもなった64a)。普通の品種の球根からも稀に高価な花が咲く、ブレイク*した花の可能性があった。そのため、まだ見ぬ花の球根が投機対象となり、先物取引が盛んに行われるようになった。しかし、この投機によって一獲千金を狙った人たちは、バブルが弾けて(1637年2月3日暴落)富を失っている(一部改)」63a)。
*普通のチューリプが変化して、多色の花をつけたり、羽状模様や炎状模様に変化したりすること。アブラムシが保毒するウイルスの感染が主な原因であった64b)。
オランダの話だが日本にも伝えられていたことは想像できる。このチューリップも多様な品種を生み出したが、鑑賞という本来の趣向から外れてしまった。チューリップはご存知のように球根(小球根)で増やせるので、高価な品種もそのまま球根によるクローン増殖ができる。つまり、ゆくゆくは、その品種を手に入れたものは増やすことができるのである(もちろん球根の増殖には年数がかかる。現在は育成者権があるので注意)。バブルはいつの時代にもある…ミーム〇〇〇か?🐶😸
**********************
靴屋が黒いチューリップの栽培に成功したことを聞きつけて、園芸家組合の一行が靴屋をおとずれ、一千五百グルデンで球根を買った。だが、球根を受け取るとすぐに、地面に投げ捨て、靴で踏みつぶした。「愚か者め。黒いチューリップなら、われわれももっている。おまえの運もここまでだ。一万グルデンだって払ってやったのに、惜しいことをしたな」・・・チューリップの花の色は黒にはならない。(エドワード・チャンセラー『バブルの歴史』より)63b)
6.動物の種の起源
〈有情の類、禽獣(とり・けもの)・魚鼈(うお・すつぽん)・昆虫の類もみな異類互に相交接して無量の形状・性状を変化し出し来るなるべし。たとへば唐犬を和犬と交感すれば必ず半犬を生ずるが如し〉
動物についてはどうか。鳥や獣、水中にすむ生き物、昆虫も、異なる類と交雑して多様な姿や形を変化させて現れてきていると述べ、例として《唐犬(海外犬)と和犬(日本の在来種)を交雑するとその子は両方の形質をもつ子となる》ことを挙げている。このように、動物でも種が異なるものどうしを交雑することで、それぞれ様々な特性、形質をもつ子孫(後代)が現れることをみている。これは、アサガオの交雑から得られた知見をあてはめて推測していると考えられる。
例えにあげたイヌのほとんどは雑種であり、多様に広がっていた犬種がいる中で、〈唐犬を和犬と交感すれば必ず半犬を生ずる〉から推測すると、生まれた子が唐犬と和犬の雑種であることを知るには、はじめから唐犬と和犬とを区別して飼い、交雑させる必要がある。そもそも江戸時代の犬の様子はどうであったのか。江戸時代には、庶民も普通に犬をペットとして飼っていて、唐犬、和犬、狆(ジャパーニーズ・チン:犬とはみなされず、室内で飼われていた)65a)と毛の長い‘むくいぬ’(のうけん:㺜犬)66)がいた。西洋からの南蛮犬(南蛮貿易で輸入)は江戸時代には唐犬(獒犬66):東南アジア経由で入ってきた西洋の犬が多い67a))と呼ばれて狩猟用の大型犬は将軍や大名らへの献上(贈答)物であった65b)。つまり、由緒ある血統の犬(グレイハウンド、マスチフなど)が輸入されている65b)。道端には雑多な犬であふれていると思われるが、南蛮屏風に描かれた犬種について「中でも興味深いのは南蛮人が連れて歩いている犬である。街角などに描かれている和犬とははっきり区別され、ヨーロッパ犬であることは明らかである」68a)とあるように、少なくとも洋犬は見た目で区別できたようだ。
中国からペキニーズ(北京狆)、またはそれに近い犬が江戸時代初期に輸入され、国内で品種改良したのが「狆」で68b), 69a)、「滝沢馬琴は当時(1827)小型犬に八種あるとして、・・・『さつまねた』は琉球狗とわが国の狗の交配によるもので、耳は垂れずその形は丸い。『まじり』は小狗と地犬との交配によるもの。また、紅毛犬(オランダ犬)と交わって生まれたもののもある(概略)。と考証、解説している」65c)とある。また、「狆」を商売しているものもいたらしく、ペットショップがあったようだ65c)。『狆飼養書』(幕末)には交雑についての詳しい記録もあり65c)、狆については品種開発も行われていたことが分かる。このことから、すでにイヌの交雑は普通に行われており、どのような種類の組み合わせでどのような形質の犬が生まれるかも分かっていたことになる。
谷口研語氏は「唐犬(南蛮犬)が、どの程度、江戸時代の在来犬と交雑したかはよくわからない。・・・交雑があったとしても、在来犬の形質を根本的に変えるような品種は、生み出されなかったといっていいいだろう」65d)と述べている。純系に近い唐犬は高価な、和犬にはない特性をもつ犬であるがゆえに、在来の和犬とを交雑して改良することを試みたが、結局は『半犬』となってしまう、つまり、子には親の形質をそれぞれから受け継いで顕性(優性)の形質が現れてしまう、という世話話を柳泓は聞き知ったのではないかと想像する。『南總里見八犬傳』(1814年初巻~1842)もベストセラーとなっていたようなので67b)、柳泓への影響もなきにしもあらず、か(仁義礼智忠信孝悌)。
もっとも、ハイイロオオカミの子孫と考えられているイヌ(始祖はまだ特定されず)70)は、古代ローマ、古代エジプト、西アジア一帯では品種改良、固定化(純系)が進められ65e)、グレイハウンド(紀元前1900頃の古代エジプトの壁画)68b)やマスチフ(2600-2650年前バビロニア、アッシリアの王宮のレリーフ69b, 69c)などは、当時の形態・体格をそのままに現代にいたっている65e)ようだ。また、古代ローマ人は犬以外の家畜の育種も始めた69b)ことが知られている。イヌの雑種については、アリストテレスの書にも「交接は同類の動物間で行われるのが自然であるが、・・・イヌやキツネやオオカミ(ヤマイヌ)の間では起こる〈イヌはキツネおよびオオカミと交尾し、その雑種は相互間でも、両親との間でも生殖力がある〉。インド犬〈ヤマイヌ?〉も或るイヌのような野獣〈トラ?〉とイヌから生まれる。」16f)とあり、また鳥や魚については「鳥類でも、たとえばシャコやニワトリのように好色なものに起こることが観察されている〈キジとニワトリは雑交する〉。また曲爪類〔猛禽類〕の中でも、タカは異種間で互いに交わると思われているし、その他の或る鳥類も同様である。海産の動物では、『サメエイ』と称するものは〔ヤスリ〕ザメと〔ガンギ〕エイが交わってできると思われている。〈 〉は註釈より」16f)とある。このように、古代より動物の交雑に関しての様々な情報(間違っているもの含め)は普通に知れ渡っていたことから、犬の例も引き合いに、〈異類互に相交接して無量の形状・性状を変化し出し来るなるべし〉と推量したと思われる。これももとを辿れば、朱子学の思想に至る。
鎌田柳泓『心学奥の桟』(1818-1822)は進化を語るのか?(中)へ続く。
「つい最近、紐を引っ張ると真ん中から分かれるカーテンを寝室の窓にかけておいた。朝わたしが起きて紐を引っ張ると、カーテンが分かれるのを見たわたしの非常に賢いプーデル*は、びっくりしてつっ立っていたが、やがてその原因を探すために、あたりをうろつき回った。変化が起こるには、その原因となるものがなにかに先行していなければならないことを、彼は、ア・プリオーリに知っていたのである(ショーペンハウアー:1788-1860)」『犬の博物誌より』68c) *犬の名
アイキャッチ画像
『心学奥の桟(上巻: 挿絵. p. 9)』(鎌田柳泓. 1822)を基に一部創作した。
座敷でキセルを吸っているのは人間に数学を授けたマヤのゼロ神である。扇子を持っているのは柳泓らしき人物と思われる。黄色朝顔を掲げているのは歌人のようである。植木職人が差し出している鉢には黒チューリップが活けてある。女が持ち帰る鉢には青いバラが咲いている(フィクション)。
花の図柄参考:ユリ:木村洋次郎・大場秀章.シーボルト『フローラ・ヤポニカ』 日本植物誌【新版】.13-1 シロカノコユリ.p. 20.八坂書房.2023.花菖蒲:安藤広重「堀切花菖蒲」より.
鉢の図柄参考:国立歴史民俗博物館.伝統の朝顔 Ⅲ ―作り手の世界―.岩渕令治.1 江戸の園芸文化の発達.参考 歌川芳藤 草花植木つくし.p. 8.国立歴史民俗博物館.2000.
引用・参考文献
1)鎌田柳泓.心学奥の棧(1822)、理學秘訣(1816)を基に以下から引用:石門心學.日本思想大系42.柴田 実 校注者.岩波書店.1971.1a)心学奥の桟 上之巻 .p. 412、1b)同.pp. 410-411.頭注、1c)理学秘訣.p. 378、1d)解説.p. 454、1e)心学奥の桟 上之巻 .(逸話)pp. 410-411、1f)同.pp. 411-412 、1g)同.p. 411.頭注.
2)カント全集9.判断力批判 下.牧野英二 訳.岩波書店.2000.2a)月報6.日高敏隆.目的論をめぐって.pp. 6-8.
3)福永光司.荘子(雑篇・下).中国古典選17.吉川幸次郎 監修.朝日新聞.1978.3a)天下篇 第三十三.p. 242.
4)市川安司・遠藤哲夫.荘子(下).新釈漢文大系.第8巻. 明治書院.1975.4a)雜篇 天下 第三十三.pp. 822-823、4b)外篇 知北遊 第二十二.pp. 576-577、 4c)同.pp. 580-581.
5)渡邊 徹.本邦最初の經驗的心理學者としての鎌田鵬の研究.中興館.1940.5a)第二章 鎌田鵬の氏名および家譜.第一節 氏名.pp. 15-17、5b) 第七章 鵬の心理思想.第二節 心理學一般.第三項「究理緒言」(「心學奥の棧」).pp. 322-333、5c)同.第二項「理學秘訣」.二、内容および構成.p. 308、5d)第五章 鵬の學統.第四節 理學.第三項 朱子の心學と鵬.pp. 222-227.
6)福永光司.荘子(内篇).中国古典選12.吉川幸次郎 監修.朝日新聞社.1978.6a) 逍遙遊篇 第一.pp.29-30.
7)市川安司.近思録.新釈漢文大系.第37巻.明治書院.1986.7a) 近思録解題.編者.p. 10.
8)中国宗教思想 2 .岩波講座 東洋思想 第十四巻.岩波書店.1990.8a)池田秀三.Ⅱ中国宗教思想の特質(続).3 存在と理法.4 不易と流行.一 理気二元論における不易と流行.pp. 48-49、8b)同.三 変易する世界.p. 52.
9)小野沢精一・福永光司・山井 湧.気の思想.東京大学出版会.1978.9a)山井 湧.第三部 理気哲学における気の概念.総論.二 理および「理の哲学」pp. 360-361、9b)同.第二章 朱熹の思想における気.一 理気論.3理と気.p. 443.
10)三浦国雄.朱子.人類の知的遺産 19.講談社.1979.10a) Ⅰ朱子の思想.2基礎諸概念.理気.pp. 18-19、10b) Ⅲ 朱子の著作.1『朱子語類』抄.五 修養論.窮理.p.298、10c)同.天理.p. 306.
11)ジョゼフ・ニーダム.中国の科学と文明.第3巻 思想史(下).思索社.1991.11a)第16章. 晉・唐間の道家と宋代の新儒家たち.(d)新儒家たち.(3)普通的パターンの研究-氣(物質=エネルギー)と理(組織)の概念.pp. 524-525.
12)福永光司.荘子(外篇・下).中国古典選15.吉川幸次郎 監修.朝日新聞.1978.12a)知北遊篇 第二十二.pp. 186-188、12b)同.p. 201.
13)ジョン・グリビン、メアリー・グリビン.進化論の進化史.水谷 淳 訳.早川書房.2022.13a) 第Ⅰ部ダーウィン以前.第2章 偽りの夜明け.pp. 55-56.
14)ヘーゲル.自然哲学(下).ヘーゲル哲学体系初期草稿(三).本多修郎 訳.未来社.1984.14a)(三)有機的なもの.二、植物的有機体.植物の成長における非有機的原素の流入.pp. 228-229.
15)ゲーテ全集 14.木村直司・高橋義人・前田富土男・永野藤夫・野村一郎・轡田 収 訳.潮出版社.1980.15a)野村一郎 訳.植物生理学の予備的研究.生理学の概念.pp. 112-113、15b)同.訳注.112.p. 490、15c)訳注.55.p. 482、15d) 植物学.第八章.雄蕊に関してなお二、三.六三、六四.p. 82.
16)アリストテレス全集 9.動物運動論 動物進行論 動物発生論.島崎三郎 訳.岩波書店.1969.16a)動物発生論.第2巻 第1章.訳者註(30)p. 346、16b)同.733b, 734a, 734b: pp. 152-154、 16c)同.735a: p. 157、16d) 第1巻第23章731a: p.143、16e)同.第8章.747a26-749a4: pp. 194-199、16f)同.第7章.746b: p. 192-193, 同.訳者注(14), (15), (16), (17), (18). p. 368.
17)Caspar F. Wolff. Theoria Generationis. Ueber die Entwicklung der Plflanzen und Thiere(1759). Ostwalds Klassiker der Exakten Wissenschaften Band 84(Reprint der Bände 84 und 85). Verlag Harri Deutsch. 1999. 17a)Dritter Theil. Ueber die organischen Naturkörper und ihre Bildung im Allgemeinen und von der Beziehung zwischen dem organischen und dem in Entwicklung begriffenen Körper. Cap. I. Ueber die organischen Naturkörper und ihre Bildung im Allgemeinen. Vergleichung der Principien und Gesetze der Entwicklung mit den Ansichten Anderer. §235. p. 144、17b)Erster Theil. Ueber die Entwicklung der Pflanzen. Cap. IV. Vom erneuerten Wachsthum. Die Befruchtung. Der männliche Same. §165. p. 88.
18)ジョゼフ・ニーダム.中国の科学と文明.第2巻 思想史(上).思索社.1991.18a)第10章 道家と道教.(b)「道」の道家的観念.pp. 45-46、18b)同.(e)変化、変形、および相対性.p. 98.
19)高柳俊哉.中江藤樹の心学-「天」について.Ⅱ 畏天命.2 朱子の「天」.p. 137.ソシオサイエンス.6.早稲田大学.2000(3).
20)田賀井 篤平.Systema Naturae ―鉱物界―.リンネの三界の中の鉱物界.東京大学総合研究博物館ニュース.ウロボス(Vol. 10/Number 1).Ouroboros 第27号.2005(5月30日).https://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DPastExh/Museum/ouroboros/10_01/jyosetsu.html
21)種村季弘.不思議な石のはなし.瀬戸 照 イラスト画.河出書房新社.1996.21a)恋する石.p. 18、21b)産む石.pp. 48-50.
22)アリストテレス全集 6.霊魂論・自然学小論集・気息について.山本光雄・副島民雄 訳.岩波書店.1968.22a)山本光雄 訳.霊魂論..第一巻第五章.411a .p. 34、22b)同.第2章.405a.p. 13.
23)ディオゲネス・ラエルティオス.ギリシア哲学者列伝(上).加来彰俊 訳.岩波書店.1990.23a)第1巻 第1章.タレス.(二四).p. 30.
24)ディオスコリデスの薬物誌.小川鼎三・柴田承二・大槻真一郎・大塚恭男・岸本良彦 編集、鷲谷いづみ 翻訳.第5巻.すべての鉱石類(海の泡、土、すすなども含む).pp. 783-824.エンタプライズ株式会社.1983.(参照:Pietro Andrea Gregorio Mattioli. Les commentaiers de M. P. Andre Matthiole, medicinale de Pedicivs Dioscoride, Anazareen. Svr Dioscor. Livre V. Des Pierres Minerales. pp. 495-543. A Lyon, Iean-Baptiste de Ville. 1680).
25)ヒッポリュトス.全異端反駁.キリスト教教父著作集 19.大貫 隆 訳.教文館. 2018.25a) 第1巻自然哲学者 クセノファネス 一四. p. 82、25b)同.アナクシマンドロス 六.p. 74.
26)島薗 進.教養としての神 道 ― 生きのびる神々.東洋経済新報社.2022.26a)はじめに.p. 1.
27)ジョゼフ・ニーダム.中国の科学と文明.第6巻 地の科学.思索社.1991.27a)第25章 鉱物学.(b)氣の理論と地中における金属の生長.pp.169-171.
28)楠山春樹.淮南子(上).新釈漢文大系.第54巻.明治書院.1979. 28a) 巻四 墬形訓 十四. pp. 237-240、28b) 同.五.pp. 214-216.
29)五十嵐健輔・柿澤茂行.硫化鉱物による化学進化と鉄イオウタンパク質の誕生.地学雑誌.129(6).853-870.2020.29a)Ⅲ. 鉄イオウワールド仮説の概要.p. 856、29b)Ⅴ. 硫化鉱物が酵素へと化学進化する過程.p. 861.
30)生命のもととなる可能性のある有機物の合成反応を実証.五十嵐健輔・Nobu Masaru Konishi・鎌田洋一ら.産総研マガジン.国立研究開発法人 産業技術総合研究所.2020(発表・掲載日:2020/03/03).https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2020/pr20200303_2/pr20200303_2.html
31)Preiner, M., Igarashi, K., Muchowska, K. B., Yu, M., Varma, S. J. Kleinermanns, K., Nobu, M. K., Kamagata, Y., Tüysüz, H., Moran, J., and Martin, W. F. A hydrogen-dependent geochemical analogue of primordial carbon and energy metabolism. Nature Ecology & Evolution. 4: 534-542. 2020. https://doi.org/10.1038/s41559-020-1125-6
32)APG牧野植物図鑑Ⅰ.邑田 仁 監修.北隆館.2014.32a)目次.p. 1、裸子植物.マツ目.マツ科、pp. 15-21、32b)被子植物.単子葉類.キジカクシ目.アヤメ科.ハナショウブ.p. 138、32c)同.ショウブ目.ショウブ科.ショウブ.p. 56.
33)近田文弘.なぜ,クロマツなのか?-日本の海岸林の防災機能について―.海岸林学会誌.12(2):23-28.2013.
34)シロマツ.「フリー百科事典 ウィキペディア日本語版」.2022年7月5日 (火) 13:13 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/シロマツ
35)進化学事典.日本進化学会 編.共立出版.2012.35a)千葉 聡.第23章 種.23.8 適応放散.pp. 784-788.
36)津村義彦.シリーズ:日本の森林樹木の地理的遺伝構造(1).スギ(ヒノキ科スギ属).森林遺伝育種.第1巻.17-22.2012.
37)Yang, Y., D. K. Ferguson, B. Liu. K. S. Mao, L. M. Gao, S. Z. Zhang, T. Wan, K. Rushorth, Z. X. Zhang. Recent advances on phylogenomics of gymnosperms and a new classification. Plant Diversity. 44. 340-350. 2022.
38)朝日百科 世界の植物 9.種子植物 Ⅸ.朝日新聞社.1979.35a)初島住彦.マキ科.イヌマキ.pp. 2431-2432、38b)倉田 悟.同.マキという木.p. 2433.
39)大学共同利用機関法人 人間文化研究機構.国文学研究資料館.国書データベース.新古今和歌集 下之二.巻第十六.https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100141478/153?ln=ja
40) 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構.国際日本文化研究センター.新古今集.新古今.巻二十:釈教.01917.異同資料句番号01920.https://lapis.nichibun.ac.jp/waka/waka_i010.html#i010-020
41)伝統の朝顔Ⅱ 芽生えから開花まで.国立歴史民俗博物館.2000.41a)仁田坂英二.Ⅰ 主要系統の芽生えから開花まで.変化朝顔とは.p. 6、41b)岩渕令治.Ⅱ 江戸時代の朝顔育成法 B『牽牛花水鏡』(前編).pp. 52-68、41c)目次(下).親木から牡丹出物ができる仕組み.p. 4.
42)園芸植物大事典 1.塚本洋太郎 総監修.小学館.1988.42a)米田芳秋.アサガオ属.pp. 57-58、42b) 津田秀樹.アサガオと園芸品種.pp. 58-61.42c)岩佐亮二.アサガオの園芸植物としての歴史.pp. 61-62
43)APG牧野植物図鑑Ⅱ.邑田 仁 監修.アサガオ.p. 273.北隆館.2015.
44)西村三郎.文明のなかの博物学.西欧と日本(上).紀伊國屋書店.2000.44a)Ⅱ章 花ひらく江戸の博物学.p. 176.
45)八十八夜園主人.牽牛花通觧(牽牛花通解) 全.東京國文社.1902年.45a)第六章 仕譯上の三區別.第一節 親木.pp. 65-67、45b)同.第二節 出物.p. 67、45c)第五章 花.第二節 三花質.第三項 牡丹.pp. 55-56、45d)同.第三節 性に専属する花.第三項 獅子性に専屬する花.p. 62、45e) 第六章.第三節 正木.pp. 67-68.
46) 仁田坂英二.変化朝顔図鑑.化学同人.2014.46a) アサガオ用語集.pp. 110-111.46b)第一部 入門編.さまざまに変化した朝顔.さまざまな変異.p.24、46c)第三部 基礎知識.遺伝の基本と「正木」「出物」.自家受粉による遺伝.pp. 94-95、46d)第一部.変異の一覧と本書で用いるアイコン.pp. 26-27、子葉の形.p. 28、第三部.p. 103.
47)Nitasaka, E. Morphological mutants induced by transposable elements in the Japanese morning glory. Gamma field symposia. 46. Institute of Radiation Breeding NIAS, Japan. 73-79. 2007. 47a)トランスポゾンによって誘発されたアサガオの有用形質.p. 79.
48)米田芳秋.アサガオ 江戸の贈りもの.裳華房.1995.48a)5章 さまざまな花と葉のかたち.pp. 49-50、48b)2章 江戸のアサガオ.1 庶民に愛されたアサガオ.p.14-15、48c)同. 2 変化アサガオはどのように.p. 17-18.
49)渡辺好孝.江戸変わり咲き朝顔.第二章 繰り返す朝顔ブーム.花の形いろいろ.獅子牡丹.p. 54. 平凡社.1996.
50)仁田坂英二.変化朝顔 種子のできない一年草.季刊「生命誌」24号.JT生命誌研究館.1999.
51)育種ハンドブック.松尾孝嶺 監修.育種ハンドブック編集委員会.養賢堂.1974.51a)角田重三郎.Ⅰ.序論.2.育種の歴史.3)遺伝質の交換の制御.pp. 5-6.
52)V. Žárský・J. Tupý. A missed anniversary : 300 years after Rudolf Jacob Camerarius’ “De sexu plantarum epistola”. 8: 375-376. Sex plant Reported. 1995.
53)Discovery of Sexuality in Plants. p. 392. Nature. March 18, 1933. https://doi.org/10.1038/131392b0
54)Rudolf Jakob Camerarius. De sexu plantarum epistola. Legare Street Press. 2022.54a)Des R. J. Camerarius Brief : Ueber das Geschlect der Planzen. pp. 53-54、54b)”pp. 49-50.
55)ライプニッツ.人間知性新論.米山 優 訳.みすず書房.1987.55a)Ⅲ 言葉について.第6章 実体の名について.p. 300.
56)Leibniz. Nouveaux essais sur L’entendement humain. GF-Flammarion. 1990. 56a)LIVRE III de mots : Chapter VI. Des noms des substances. pp. 241-242.
57)ピータ―・J・ボウラー.進化思想の歴史(上).鈴木善次・横山輝雄・森脇靖子・田中紫枝・柴田和子・斎藤 光・大林雅之 訳.朝日新書335.朝日新聞社.1987.57a) 田中紫枝.6 ダーウィニズムの起源.pp.267-268.
58)Erasmaus Darwin. Zoonomia. Or, the laws of organic life (1). The second edition, corrected. HardPress. 2016(Copyright). 58a) SECT. XXXIX. II. 2. p. 477.
59)Goethe. Naturwissenschaftliche Schriften. I. Die Metamorphose der Pflanzen. Rudolf Steiner Verlag. 1982. 59a)VIII. Noch einiges von den Staubwerkzeugen. 64 : p. 39.
60)西村三郎.文明のなかの博物学.西欧と日本(下).紀伊國屋書店.2000.60a)Ⅵ章 博物学の黄金時代を招来したもの.p. 387.
61)冨野耕治・堀中 明.花と木の文化 花菖蒲.塚本洋太郎 監修.家の光協会.1980.61a) 冨野耕治.序章 日本のアヤメの仲間.ハナショウブとショウブとの違い.p. 23、61b)第1章 ハナショウブ発達の歴史.pp. 29-33.
62)園芸植物大事典 3.塚本洋太郎 総監修.小学館.1989.62a)冨野耕治・塚本洋太郎.ハナショウブ.pp. 587-593.
63)エドワード・チャンセラー.バブルの歴史.山岡洋一 訳.日経BP社.2000.63a)第1章 このバブルの世界 ― 金融投機の起源.チューリップ狂.pp. 37-45.63b)同.シャボン玉消えた—投機の寓話と伝説.pp. 47-48(アレクサンドル・デュマ『黒いチューリップ』).
64)アンナ・パヴォード.チューリップ ―ヨーロッパを狂わせた花の歴史―.白幡節子 訳.大修館書店.2001.64a)第4章 チューリップ狂時代.pp. 126-127、64b)序.p. xviii.
65)谷口研語.犬の日本史.吉川弘文館.2012.65a)第五章 海外からやってきた犬.p. 84、65b)同.pp. 74-77、65c)同.pp. 81-83、65d)同.p. 79、65e)同.p. 73.
66)頭書増補訓蒙圖彙巻之十二.畜獣.十.獒犬(たうけん)・犬(けん)・㺜犬(むくいぬ).p. 10.1695.
67)仁科邦夫.犬たちの江戸時代.草思社.2019.67a)第三章 江戸初期の犬事情(二)御鷹餌犬と鷹狩.1 無類の鷹好き徳川家康.日本一の鷹持ち、犬持ち.p. 123、67b)第一章 花のお江戸は犬ばかり.4 江戸と上方、犬の糞比べ.『八犬伝』の著者の犬トラブル.pp. 47-48.
68)愛犬の友編集部.犬の博物誌.誠文堂新光社.1981.68a)岡田章雄.南蛮屏風と南蛮人.p. 80、68b)内田 享.今の犬種のできるまで.pp. 38-41、68c)塩屋竹男.哲学者の見た犬.p. 25.
69)正田陽一 編著.人間がつくった動物たち.東書選書.1987.69a)犬、猫.犬. 二. 日本犬の成立.p. 178、69b)同.一. 犬の家畜化.pp. 171-172、69c)同.三. 西欧の主な犬種.pp. 182-183.
70)イヌ全史.―君たちはなぜそんなに愛してくれるのか―.尾崎憲和 編集人.田島 進 編集.喜多直子 翻訳.トランネット 翻訳協力. CHAPTER 1. 野生のオオカミから番犬へ.イヌの昔と今.pp. 8-10.ナショナル ジオグラフィック 別冊.日経BP.2023.