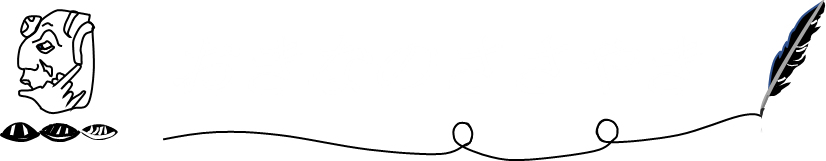桃に生る虫を桃むしと云、栗に生る虫を栗虫といふ、地球に生るを人間といふ
司馬江漢『独笑妄言』103b)
10.これは果たして西欧思想か? (1)地球のこと 生命の発生
柳泓は、西欧の自然科学的知識に接する機会が多かったことは確かである。養父の一窓とともに古医方を学んだとされ1j)、五根(眼・耳・鼻・舌・身:六根では「意」が加わる)の知識を統一するものを「蘭人ハ頭脳ノ中チニ在リト云フ」1k)と紹介している。『理学秘訣』には『西洋』という言葉がところどころ出てくる。日本に初めてアリストテレス流の西洋自然学106)(哲学・天文學等)を紹介・解説した澤野忠庵(Christóvão Ferreira)らの『乾坤弁説』(1659)をはじめ、司馬江漢『和蘭天説』(1796)などを参考にしたと思われる論も見受けられる。渡邊 氏は『理学秘訣』の自然科学思想について、解剖學や生理学は杉田玄白『解體新書』、宇田川玄眞『醫範提綱』、天文・氣象、物理の論述は向井玄松『乾坤辨説』、西川正休(訓点)『天經或問」、世界地理は司馬江漢『地球全圖略説』の書に負うものとして、特に『乾坤弁説』との立論順序と内容の類似性を挙げている5g)。また、柳泓と同じ学統の木門に属するとされる新井白石の影響5f)(西洋思想と共に鬼神論など)も大きいと考えられる。
ここでは進化思想の糸口となるかもしれない〔地球〕〔生命の発生〕〔三行説〕について西洋思想とのかかわりをみてみたい。
『心学奥の桟』の〈地底は皆岩石にて土は只餅上の豆粉の如くなるの説〉(土壌(豆粉)は岩石(餅)の上にのっているようなもの)1l)について、西洋流の地表・地殻説を取り入れていると注釈されている1l)。どの説を基にしているかは分からないが、デカルトの『哲学の原理』(Principia Philosophiæ:1644)の‛地球の内部構造’107a)、この時代であればビュフォン『博物誌』(1749)の地球の表層108a)について聞き知ったのか。司馬江漢の「土ハ水上ノ塵埃ノゴトシ」109a)に近いと思うのだが。
また、同じ説の中で「土壌より湿熱の気に因て、草木・禽獣・虫魚・人物等を生じて、互に相喰て以て生養する者なり。・・・地底に猶水火を孕て湿熱を生じ、万物生々の原となる事は、先に理学秘訣に於て論じて・・」1m)とある。これについて『理学秘訣』をみると、〔問、地火トハ何ンゾヤ〕「曰、大地ハ裡ニ内火ヲ含メリ。西洋ニテハ是レヲ地火ト云フ。其ノ発シテ地上ニ顕ルヽ者ハ、・・・西域ノ火山、日東ニテハ富士・浅間・阿曾・霧島・・・又地震ナンドモ、皆此ノ地火ノ動揺也。・・・又海水ハ、本大地卑下ノ処へ衆水ノ滙セシ者ニテ、本醎味アルコトナシ。其ノ鹹味ヲ成スハ、皆地火ニ煎ラレテ、是レヲ生ゼリ。是レ西洋ノ説ナレドモ、暗ニ尾閭焦石ノ説ニ合セリ・・・サテ大地ノ中チ、地火ハ最モ裡チニアリ、其ノ表ハ水ヲ含メリ。・・・サテ右地底ノ内火、表ノ水気ニ和合シテ、地上ニ蒸騰シ、天気ニ応答シテ、化シテ露トナリ霜トナリ、霧トナリ雲トナリ、雨トナリ雪トナリテ、万物ヲ生々セリ。是レ易象水火既済ノ理ニヒトシ」1n)、と西洋(オランダ)の知識から地核に火があることを述べ、地底の火と地表の水の気が和同して立ち昇り、万物が生々することが書かれている。
さて、西洋の地火、火山と地震、はどこからの書か?
ここでアリストテレスの地球の地下と地震の論について記す。「風に続いて大地の揺れと震え〔地震〕について論じなければならない。というのも、この現象の原因は風のそれにまったく近いからである(地震は風と同じく大地からの乾いた蒸発物に起因する現象)110a)。・・・大地の震動の原因は水でもなく、土でもなく、むしろ風であり、大地の外へ蒸発したものが内へ流れ込むときにそれが起こるのでなければならない。・・・地震が起こると水が噴き出すということがしばしばあった。(これは)風が大地の表面に沿って、あるいは地下から水をおしやるのである110b)・・・同じ実体(乾いた蒸発物)が大地の上では風となり、大地の下では地震となり、雲のなかでは雷鳴となる110c)(概略)」、とさまざまな現象や地震の前兆(直線状の縦じまの雲の出現)110b)なども記し、興味ある論が展開されている。さらに、「大地もまた、そのなかに、水ばかりでなく、風や火の多くの源泉を抱擁している。地下にあるものは目にみえないが、火山のように噴気孔や通風孔をもっている。或るものどもは、地下で水源の近くにあって、これらに熱をあたえる、ときには適度に混合した温度の流れを噴き出す。同様に、風についても、通風口が地上の多くのところで小さな口をあけている。しばしば連続的に地の中で適度に混合され風が、地の深い洞穴に押しこまれて、それに固有な場所から追い出されると、多くの場所で衝撃を起こす。また、しばしば多くの風が外から入ってきて地の穴にとじ込められ、出口をふさがれると、自分の出口を求めて地を強く揺さぶる、そして、地震と呼びならわしている、この震動の状態をつくり出す(一部略)」110d)と論じ、この『風』による地震の説が後の時代にも大きな影響を及ぼすことになる。
アグリコラ(Agricolae)の『De Ortu et Causis Subterraneorum(地下の起源と原因について)』(1546)には、古代ギリキャ人の述べた論を中心に、地震については(正しく解読できているか疑)地下の洞窟(空洞)の崩壊など?(エピクロス)、地下の水(タレス、デモクリトス)、内部の風(アリストテレス、テオフラストス)、あるいは火が要因(アナクサゴラス:エーテルという火により洞窟が動く)―地中の熱や火が蒸気を生成し膨張し出口を求める、また地震で揺れることによる噴火、地震によってできた山(Modernu)なども記されているが111a)、彼の書が日本に移入された記録はみられない。
他の情報源として、ビュフォン『博物誌』(1749)の‘地球内部の熱の理論’82c),108b)、地殻・地核や地震108c)、ハットンの『地球の理論』(1795)の‘地球内部のマグマ、地層形成’112a)などある中で、最も確からしいのは、アタナシウス・キルヒャー(Athanasius Kircher: 1602-1680)『Mundus subterraneus(地下世界)』(1665)からの情報と思われる。本書の「月」と「太陽」の図113a, b)を司馬江漢が『天球全図』の中で「大陽真形」および「月輪真形」として描いている109b, c), 114a)。その説明に「図スル所大陽ノ真形ハ、和蘭書中ニ載スル者ヲ以テ摸刻ス」109b)、「月ノ図ハ、和蘭書中ニ載ル者ヲ以テ模写ス」109c)とあり、蘭書とはいうまでもなくキルヒャーの『d’ONDER-AARDSE WEERELD(地下世界)』(1682)115a)である。まさしく「大地ハ山川海河ヲ戴テ、外堅実、必内空ニシテ、天ニ浮ミ、地中自ラ水脈ト火脈アリ・・・」109d)である。司馬江漢と柳泓の直接の接点は分からないが、鎌田家の養子となった鎌田恵迪、親類の山田道貞、友人の金子風竹らが司馬江漢と会っている(1812年)5h)。柳泓は、彼らから司馬江漢を通じて《地球内部の火(地核の火)》115b)を知ったはずである。すなわち、柳泓の〈大地ハ裡ニ内火ヲ含メリ。西洋ニテハ是ヲ地火ト云フ〉はキルヒャーの〔地核の火〕から得た知識であると思われる。地震についても地球の内部の火と、火山とともに述べられており115c)、〈地震ナンドモ、皆此ノ地火ノ動揺也〉はこの蘭書の話をもとにしたのではないかと推測される。
しかし、司馬江漢は「震ハ常ニ地気上升スルト雖、地中に鬱滞シ遽ニ発ル者ナリ、地気升コト処トシテ剛柔アリ、地中濃ナル所アリ、麁疎ナルアリ、」109e, f)と述べ、『乾坤弁説』の「土中の風大出んとする時、地體動する・・・」116a)と書かれたアリストテレスの論110b)と同様であり、「地火」と「地震」との関係については出てこない。
そこで、ビュフォンの書をみると「地震を引き起こす原因には 二つあり、ひとつは地球内部の空洞が突然崩壊することで、二つめは一つめよりもさらに頻繁で激しい地下の火の作用である。地下の火によって引き起こされるこれらの地震は、通常、火山の噴火に先立ち、火山の噴火とともに止まる。・・・したがって、すべての地震は三つの原因に集約される。最初の最も単純な原因は、地下空洞の突然の崩壊である。二つ目は地下の嵐と雷の衝撃。そして三つ目は、地球の内部で燃える火の作用と応力である。私には地震に伴うすべての現象は、これら三つのうちいずれかが原因であると考えられる(おきな訳):IL y a deux causes qui produisent les tremblemens de Terre, la première est l’a ffaissement subit des cavités de la Terre, & la seconde encore plus fréquente & plus violente que la première, est l’action des feux souterrains. Ces tremblemens de terre, causés par las feux souterrains, précèdent ordinairement les éruptions des volcans & cessent avec elles, ・・・Nous réduirons donc à trois causes tous les mouvemens convulsifs de la terre, la première & la plus simple, est l’affaissement subit des caverns; la seconde les orages & les coups de foudre souterraine; & la troisième l’action & les efforts des feux allumés dans l’intérieur du globe : il me paroît (paraît) qu’il est aisé de rapporter à l’une de ces trois causes tous les phénomènes qui accompagnent ou suivent les tremblemens de terre.」117a)とあり、火山と地震との関係性を明記している。柳泓は『地気』ではなく『地火』と記していることから、この説をどこかで聞いたのかもしれない。
西洋の天文学を紹介した山片蟠桃(1748-1821)の『夢ノ代』(1802-1820)に記述されている「富士・浅間・阿蘇・霧島・雲仙・由布」118a)の火山活動について、その列挙の順や説明には類似性がみられるが、そこまでである。
鹹の話 〈海水ハ、本大地卑下ノ処へ衆水ノ滙セシ者ニテ、本醎味アルコトナシ。其ノ鹹味ヲ成スハ、皆地火ニ煎ラレテ、是レヲ生ゼリ。是レ西洋ノ説ナレドモ、暗ニ尾閭焦石ノ説ニ合セリ〉
自然科学思想の源泉のひとつとして指摘される『乾坤弁説』には、海水からの塩の形成について「海水は熱燥の氣に煎熱煮焦せられて、鹹き味生ずるなり」116b)とあり、ほぼ同じである。前文は、司馬江漢「水ノ本来味ナシ、鹹元水体ニ非ス、海水地ニ入テ砂石ノ上ヲ経テ、湿液滲漉シテ其鹹気ヲ去ラシム」109g)にみえる。柳泓は、これは西洋の説というが、尾閭焦石ノ説 1n)(焼けた石を用いて海水から塩を得る)†にあると、論じている。 †おきな釈
天地と万物生々 『乾坤弁説』の‘風’を述べる中で「地水の二大よりする時・・・風中に生ずる十二品あり、露、霜、霧、霞、雲、雨、雪・・・生じ、・・・。陰陽五行の氣、升降浮沈往来循環する事、是天地の政也、天道大徳の化也、是に依て萬物の生成あり(抜粋)」116c)と柳泓の「地底ノ内火、表ノ水気ニ和合シテ、地上ニ蒸騰シ、天気ニ応答シテ、化シテ露トナリ霜トナリ、霧トナリ雲トナリ、雨トナリ雪トナリテ、万物ヲ生々セリ」と関連がみられる。しかし、『乾坤弁説』には〈地底の火気と地上の水気の和合〉の表現はみられない。
火気と水気が和同して万物が生々することは、柳泓によれば『易經』の六爻の卦【既濟】(離下坎上:火(離)が下で水(坎)が上)の理(完成.成就)18d)に等しいという。つまり、この西洋の説(哲学)はすでに東洋にあるという。とはいえ、司馬江漢の書にある「我国に鬼神を論ずる者あり、誠に愚論と云ふべし、鬼神とは水火の二気を云ふ。天の火気地に徹し、地の水気と相混合して升降す」103c), 104b)、「天気地ニ徹透シテ地ヨリ為所ニシテ万物ヲ助成シ造化ス、・・・天気ハ物ヲ育シ、地気天気ニ雑テ万物ヲ助成ス」109h)、とあり、《天の火氣と地の水気の和合、天気の応答、そして万物生々・・》の論旨に近く、加えて「虚空の天中日気にして冷際の下水火の気也、水火を以造物者とし、森羅万象悉く此二気より生して造化をなす、天の大機無窮の妙とや云ん」103b)は柳泓に通じるものがある。
湿熱 〔問、仏教ノ四生ハイカン〕「曰、・・・四生*ニ分ルトイエドモ、其ノ実ハ皆湿生ニ出デズ。天地ノ間ダハ、水火土ノ気常ニ蒸シテ湿熱ヲ生ゼリ。是レニ因ツテ万物ヲ生々ス」1o)といい、万物生々に共通の理念がみられる。
*佛教の胎生・卵生・化生・湿生:一切の生き物をその生まれ方で分類。化生は忽然として生まれたもの119a)
この佛教の説について渡邊 氏は、「天地の間に水・火・土の氣が常に蒸して濕熱を生じ、これによって萬物が生生する」としている5i)。しかし、柳泓は「物の変化はすべて湿熱の気によれり」1p)、また〔草木の花実・枝葉・人物の形状・性情(こころ)、皆本来空中に含蔵するの理に因て変化し来るの説〕で「空中水火の気を含て各々種々の紋理をなせり」1p)とも記している。これらから類推するに、《気が蒸して湿熱を生じる》のではなく、《天地の間にある、火の気と水の気とが合して(地底ノ内火、表ノ水気ニ和合シテ)『湿熱の気』となり、万物を生む》のである。しかも、それをうごかす『理』は空中に存在(含蔵)するのである。さて、ここで注目すべきは『湿熱』である。なぜ、突然でてきたのか?
西欧の生命の発生について、アリストテレスは「いかなる生物も〔熱によって成熟して〕生ずるのである。・・・動物や植物は土の中や水の中に生ずるが、これは土の中に水があり、水の中には気息(空気)があり、すべての気息の中には霊魂の熱があるからで、したがって、或る意味ではすべてのものが霊魂に満ちているわけである。それゆえ、霊魂が取りこめられさえすれば、生物はすぐに形成されるのである」16g)、と「土、水、気息(霊魂)、熱」のキーワードがある。しかし、いうまでもなくこの「気息」と儒学の「気」とは異なる11c)。湿熱からの万物生成としては、アナクシマンドロスの述べる「最初の生物は湿ったものの中で生まれ、・・・(アエティオス)」87a)、「動物たちは〈湿ったものが〉太陽によって蒸発することから生じた(生物は湿ったものの中から太陽の蒸発作用を受けて発生した)」25b), 87a)には近い。『乾坤弁説』では、「異國には地水風火の四大を萬物の本と用る也、其故は萬物の生滅は、寒熱濕乾の相生、相克に有る物也、剋するときんば物滅す、相生するときは物生ず、然るに相生することは、四品より外なし、曰熱燥、濕温、寒濕、燥寒是也、此て四品の相生は、即地水風火の性也、然るときんば地水風火の四つより外、萬物の本となる物なし」116d)と説明が以後続くが、南蛮學には湿熱を基とする万物生成論はみられない。一方、儒家の説として「天地兩間の氣は(南蛮學の)四大の氣に非ず、五行の氣天地の兩間に瀰滿したるもの他、此氣を氤氲と云、此氤氲の氣は五行和合の氣也、故に此氣中に寒熱温冷燥濕の化あり、又陰陽升降の性あり、天の氣降、地の氣升、五行の氣相和交密して萬物生ず」116e)を挙げており、どうやら天地の間の『氤氲(氳)』(氳は霧のような湿った状態)がポイントで、萬物生々を担うようである。この言葉は『易経』にあり、「天地絪縕*(氤氲) 萬物化醇 男女構レ精 万物化生(天地の間の気が密接に交じり合って万物がそこに形をとってあらわれてくる。男女が精を合わせることによるように万物が形をとって生まれてくる)」120a)。また『白虎通(義)』(嫁娶)にも「易曰天地氤氳萬物化淳男女構淸萬物化生人承天地施陰陽」121)と引用されている。『絪縕』は、さかんに交じりあうさま、天地の気の交わりで、『化醇』は天地の交わりによって、酒精が発酵によって生まれてくるように、万物がさかんに生成されてくることである120a)。また宋の張栻によれば、「絪気は之れ相因り、縕気は之れ相温(あたたむ)。相因りて以て合を為し、相温めて以て和を為す」120a)と解釈され、『濕熱』のようでもある。柳泓はこの天地中の『氤氲』(暖かな湿った氣)を湿熱ととらえ、そこから生命の誕生をみたのかもしれない。 *釈文
ところが、である。山片蟠桃の『夢ノ代』(1802-1820)では「我地球ニ似タルモノナレバ、ミナ土ニシテ湿気ナルベシ。・・・太陽ノ光明ヲ受テ和合セザルコトナカルベキヤ。スデニ和合スレバ水火行ハレテ(この二つが協力して諸物を生ずる)、草木ノ生ゼラルコトナシ(生じないことはない)。又虫ハ本ヨリ生ズベシ。虫アレバ魚貝・禽獣ナキコトアタハズ」118b)と論じている。また、蟠桃は天を「熱際・寒際・湿際の三際とし、さらに地表下近くに水際を考える。これによって全般的な気象現象を説明しようとした」118c)とあり(西欧伝来では熱際、温際、冷際の三際)118c, 122a)、そこから「太陽ニ近キヲ熱際トシ、遠キヲ寒際トス。ソノ明ハ及ブ(ト)イエドモ、其熱ハ及バザルヲ以テナリ。シカレドモ星ニアヘバ、其熱激シテ星ノ水気ニ和シテ湿トナル。仮ニ名ヲ湿際ト云。コヽヲ以テ寒暑陰陽行ハレテ万物生々スル也」118d)と論じる。ここに、水火の和合により、湿となることが示され、ここから万物が生み出されるのである。つまり、鎌田柳泓と同年代で近くの大阪に住んでいた山片蟠桃の思想(極めてラジカルであるが儒の思想ももつ)にも触れていると考えることは想像に難くない。蟠桃に触発されて柳泓オリジナルの『水火の気+湿熱』による生物発生論を創りあげた、と考えるのもありか。
このように、柳泓は知人や書を通して多くの西洋の自然科学的知識を会得しているが、しかし、柳泓のスタンスは、西洋の知識をそのまま受け入れて説くのではなく、東洋思想との関連を吟味して問うているようである。いや、むしろ西洋の学説は既に東洋にあったことを主張したいようにも思える。
10.(2) 柳泓の三行説は模倣か
さて、前述しているこの世の存在するものを形作る基本要素(ストイケオン:stoicheion)について、さらにみてみたい。柳泓は天地の間に形をなす者として‟水、火、土”を挙げた。渡邊 氏は「鵬は特色ある三行説とも名づくべき起源不明の見解を提出している。支那の五行、印度の五大、それから西洋の四行を見て、遂に三行説を出すに至ったのではあるまいか。江漢は二行説である」5j)としているが、果たして?
『理学秘訣』で〔問、天地ノ間成ㇾ形者、幾許カアルヤ〕「曰、天地ノ間ニ形ヲ成ス者ハ、水火土ノ三ツ也。気ハ又其ノ水火土ノ三ヲ生ズル本也」1q)と述べている。続けて「儒ニ金木ヲ加ヘテ五行トスレドモ、金木ハ本土中二生ズレバ、土ヲ云ヘバ金木ヲ包ベシ・・・・又仏家ニハ地水火風空ヲ以ツテ五大トス。此ノ中チ地水火ハ水火土也。空ハ即チ気ナリ。唯ダ風ハ本ト水火ノ気激動シテ、空気ヲ扇者ナレバ、水火空ノ外ニ、別ニ一物トスベカラズ」1q)」とあり、渡邊 氏は「儒家では金・木を加えて五行とするけれども、金・木は土中に生ずるものであるから、土といへば金・木を包ねる。佛家では地水火風空の五大とするけれども、地水火は水火土で、空は氣である。風はもと水火の氣が激動して空氣を扇ぐものであるから、水火空の外に一物としてはいけない5k)」と解説している。
これについて、「乾坤辨説」(1659頃)に「南蠻學の説には、萬物の本元は土水風火之四大也、此四大和合して萬物生成する物也。・・・天竺の學術は佛家之學也、其説には地水風火之四大を、萬物生成の元體本質とせり、生往壞空の四義を以て、萬物生成の象とせり、本より理氣陰陽之説なし、四大の外に空を立て、五輪之説をなすと雖、空とは萬物色體の本質に非ず、是四大和合、融通無碍の處を指て空と云ならん、故に空をば無碍也と釋す、・・・四大和合、無碍融通して、妙合の機動じて萬物出生す」116f)と、『空』は本元でないことが記されている。この書も読んでいるだろうが、柳泓は『空』†は『氣』であり、ものを成す要素とはならないとする。†後述するが、柳泓は『空』=『太虚』=『天』=『気』と考える。
『風』は水火の気によって動くもので本元ではないことについて「吹火偶ヲ見テ知ルベシ。其ノ製小キ達磨の像・・・(水の入った)偶人ヲ熱スレバ、孔ヨリ火ヲ吹キ活コト盛ン也・・水尽クレバ、忽然トシテ息ム。是水火ノ激シテ風ヲ生ズルノ証也。・・・天地ノ間ハ、陰陽の気常ニ相ヒ推シテ屈伸スル也」1r)と長々と論じているが、『乾坤弁説』に「火吹玉(達磨)と云物あり、内に水を入て火中にて焼く時、口より氣を吹出すが如し、・・・吹風は天地の間の囊籥、火吹玉の氣を吹き出すが如し」116g)と同様な文言があり、『風』は『水火』によって『空気』を扇ぐもので、ものを成す要素とはならない(水火空の外に一物とせず)ということか。ついでながら、『風』について仏教では「風界には動く物質の集合体に含まれていて、そのものを動かすという性質のものと、動かない物質の集合体に含まれていて、その集合要素が互いに離れないように支えている性質のものとがある」123a)という概念があるようだ。
ここまで述べてではあるが、渡邊 氏は「江漢は二行説である。『春波楼筆記』(1811未刊行)に記されているが鵬はこれを見ていない(一部改)」5j)としている。(見聞した可能性はあると考える)。しかしである。司馬江漢の『和蘭天説』「天気地気ヲ推トキハ二気相逼テ風ヲ生ス①、総テ天地皆気中ノ大機ヲ爲、大気是ヲ包ムト云、其根元ハ大陽一物ニ帰ス、土木水金皆大陽ノ火気ヲ得テ生シ、故ニ火ハ是最神ナリ、西洋ニテハ金木ヲ捨テ水火土トス②、・・・木ト金トヲ火中ニイルレバ、木ハヿ僅ニ灰塵トナツテ不レ存、金ハ火得テ愈精乄不レ滅、土金ヲ生ト云、土ノ木ヲ生ズル③カ如クナラズ、金土中ニ生スト雖、水ハ不レ生、・・・気ハ火ト水ニ乄一也・・・古人ノ曰、鬼神トハ天地ノ中、天気ノ陽ト地気ノ陰トノ二気ノ動テ伸屈ミスル④ヲ云也」109i), 122b)にすべてが言い尽くされている。すなわち柳泓の〈水火土ノ三ツ也〉は「西洋ニテハ金木ヲ捨テ水火土トス」②、〈金木ハ本土中二生ズレバ、土ヲ云ヘバ金木ヲ包ベシ〉は「土金ヲ生ト云、土ノ木ヲ生ズル」③、〈水火ノ気、空気ヲ扇者ナレバ〉は「天気地気ヲ推トキハ二気相逼テ風ヲ生ス」①(天気は火気109j)、地気は水気109h))、〈天地ノ間ハ、陰陽の気常ニ相ヒ推シテ屈伸スル也〉1r)は「天気の陽と地気ノ陰トノ二気ノ動テ屈伸ミスル」④と、柳泓の『三行説』の着想はほぼ江漢の書より出でたものと考えうる。先述の〈我国に鬼神を論ずる者あり、誠に愚論と云ふべし〉103c)はカチンとくるところであろうが、柳泓はその思想を受け入れたのか「天地日月、山嶽江瀆より竈の神・井の神・中霤、門行等の神に至っても又皆一理の變化のみありて各々其神ある事なし」1s)と、理による変化(一気からの化成)を認めるが、「鬼神」の実在を否定5f)している。「鬼神」という机上のものから「水火」という物理的にとらえることのできるものへの思考の転換である。
ところで、この世の根源なるもの(アルケー:ἀρχή:始原)、あるいは物質を構成する基本要素(ストイケオン: stoicheia、元素:elemnt)は古代ギリシア哲学を思い浮かべて西欧に由来する、と思われがちであるが ―― 例えば、タレス(前624-前546)はアルケーとして『水』、アナクシマンドロス(前560頃)は存在するものの元のもの(始原)として『ト・アペイロン(無限なるもの)』、元素として『水、火、空気、土』、エンペドクレス(前450頃)は根(rhizomata)の『水、火、土、空気』、アリストテレスはストイケアの『水、火、土、空気』を認めながら『湿、乾、冷、熱の4性質』としたのである18e) ―― しかし、管仲(管子)(前730頃-前645)はタレスより先立つこと『水』は万物の本源であり、あらゆる生物の宗宔(根源)であると説く9c)。「水者何(具レ材)也 萬物之本原也 諸生之宗宔也」124a)。万物生成の根幹をなすものとして水を『地の血気』としてとらえ、草木鳥獣も水を得て生育するとともに、九徳(仁・知・義・行・潔・勇・精・容・辞)を具える。
「地者萬物之本源 諸生之根荄也 美惡賢不肖愚俊之所レ生也 水者地之血氣 如ニ筋脈之通流一者也 故曰 水具レ材也(大地は万物を生み出す本源であり、生物にとって基盤となるものである。人をはじめとする鳥獣草木の美悪賢愚のすべてが生じる所である。その一方、水は大地にとって血液であり、体内を血管によって血液が流通しているようなものである。それゆえに『水はすぐれた徳性を具備している』と言われるのである)」124b)。面白いことに、『水』に人格(徳)を与えていることである。「人皆赴レ高 己獨赴レ下 卑也 卑也者 道之室 王者之器也(人は皆高い所へ登ることを望むのに、水はだけは低い所へと流れ下るのは、謙虚の性格を備えているのである。謙虚であることは、道の留まり宿るところであり、天下の王者の用いる徳性である)」124b)と。このようなことはガッコウでは学ばず、情けないかな西欧一辺倒である。
遅ればせながら、陰陽家(騶衍:前350?-前270?)を起源とされる五行18f)「水、火、木、金、土(生序:宇宙発生論の順)」18g)(この五つが順序に従って循環するので五行という。「行」はめぐる意7c)、現代は金木水火土。相生、相勝の順もある)、佛家(天竺の學術)の「地水風火」の四大(あるいは「地水火風空」の五輪)116f)と、物質を構成する根元となる元素の哲学的思想は古来より厳然としてある。ニーダムは「一般的にみてギリシアの元素説と中国の五行説にはいくらか相似性があるということもできるが、相違の方が顕著であり、伝播を仮定する必要はないかにみえる」18e)としている。
結論として、古代ギリシアの基本要素は、先に挙げた『乾坤弁説』に南蠻學の説として「萬物の本元は土水風火之四大也」116f)が紹介されているところであるが、司馬江漢の『和蘭天説』には西欧の説として《水火土》の3つであるように記している。柳泓は総合的に勘案してこれを【三行説】として採用したと推察される。
以上、柳泓と西欧思想とのかかわりを視点を変えて覗いてみたが、進化に結びつく論者は見当たらない(ビュフォンについては(中)8.萬物の変化で言及した)。
11.ここで、もう一度<無、極、虚、有、気・理><道>天地を紐解いてみよう
《天地ハ何ニ物ゾヤ。天地は一気也。天ハ即チ太虚ニシテ、地ヲ離ル、以上ハ皆天地也》1t) 柳泓のもつ哲学・思想に迫るには外せない。
『老子』(道徳経)の「無レ名 天地之始 有レ名 萬物之母(體道第一)」125a)は、「<原初>なる『無』から<現象>としての『有」が生じる』」の意126a)と説く。老子における生成論は根源としての「道」=「無」8c)(『道』と同義であり、またその一側面)であり、その『無』から『有』が生じる。「有レ物混成 先ニ天地一生 寂兮寥兮 獨立而不レ改 周行而不レ殆 可三以爲ニ天下母一 吾不レ知ニ其名一 字レ之曰レ道 强爲ニ之名一曰レ大(象元第二十五)」(はじめに混沌とした何物かがあった。それは天地の分かれる以前から生じていた。それは声もなく姿もない存在であるが(寂かなこと、空虚なこと)、他の何物にも頼らず存立し(自給自足的)、不変のものであり、万物にあまねく行きわたっていて、しかも怠らない(尽きない)。それが天地万物を産み出したのであるから、天下の母であるということが出来よう。私はそのものの名を知らない。だから、これに字して(儀礼上の名称)道と言い、しいて名づけて大と言うのである)18h), 125b)。
道について・・・理法的存在か物質的存在か
松村 巧 氏は、『老子』は「天地に先行し、天地の万物の根源をなす真実在を仮に『道』と名づけた」8c)とし、(去用第四十)「天下萬物生二於有一 有生二於無一:天下の万物有より生じ、有は無より生ず」125c)および(道化第四十二)「道生レ一 一生レ二 二生レ三 三生二萬物一 萬物負レ陰而抱レ陽 冲氣以爲レ和(道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生ず。万物は陰を負い陽を抱き、冲気*は以て和を為す)」8c), 125d)より、「一は一気、二は陰陽の二気、三は陰陽の二気と冲気とを合わせたもので、『有』とは『気』である(一部略)」8c)と述べる。ゆえに「道」=「無」は「有」=「一気」に先行する8c)といえる。同じく、『淮南子』(天文訓:一)に「太始(道)は虚霩に始まる。虚霩は宇宙を生じ、宇宙は気を生ず」8c), 28e)より、万物の根源としての『道』=『無』であり、『一』=『気』との間には隔絶があり、「その場合の『道』は物質的属性や時空の範疇を越えた理法的存在を志向する(改)」8c)ものである。しかしながら、『淮南子』(天文訓:十四)に書かれている「道は一に始まる。一にして生ぜず、故に分かれて陰陽と為る。陰陽、和を合して、万物生ず」8c), 28f)は、『道』=『一(気)』と同位の概念で、その生成論は『気』一元論を志向する」8c)とも解釈される。このように『老子』の説く『道』の在り方については「究極の拠り所を物質次元に求めるか、それを超えた次元(理法的存在)に求めるか」8c)という、いずれでもありうる概念が併存し、後の思想家にも影響を及ぼしている。 *冲氣:陰陽二気によって湧き起こった気。
万物斉同 自生自化 続けて『道』をみると、『荘子』に「道すなわち真実在の世界は、常識的な思考における大小を超えている。・・・それは道が『物の量は窮まり無く、時は止まること無く、分は常無く、終始は故無し』- 万物の数量は無限に大きくて測り知られず、時間は刻々に流転して一瞬も止まることがなく、「分」すなわち万物のそれぞれに与えられた境遇は一定不変のものでなく、一切存在は終ってはまた始まり、始まってはまた終わる不断の変化のなかで『故』すなわち旧態をとどむるものは何ひとつない」75c)。とある。また、同様な語りとして「古人も"道は通じて一と為す"といっているように、万物は『道』において斉一であり、そこではいずれが短、いずれが長ということもないのだ。道はあらゆる時間的な限定を超えているから、始めもなく終わりもなく、無始から無終に至る果てしなき変化の流れであるが、その流れの中で生滅する万物は有限の存在であり、死しては生じ、生じてはまた死んでゆく」75d)(万物斉同:多と一、物と我、生と死、古と今とが、『道』において斉しい)8d)。「道はまた・・・一切万物を生成化育しながらその成果を誇ることがなく、あるいは虚となり、あるいは満となる盈虚盛衰を自然の推移に任せて、一瞬も旧き形に止まることがない」75d)という。
また、ここに「何爲乎 何不爲乎 夫固將自化」(何をか為さんや、何をか為さざらんや、夫れ固より将に自化せんとす)75d) ―― 万物の自生自化 ―― 自ずから生じ、自ずから化す ―― を道とする思想75e)が示され、福永氏は「万物のなかに道を、変化のなかに不変を、現在のなかに永遠を凝視しようとする汎神論的な思考が成立する」75e)と論じている。
「太虚」は「太極」とは異なる 柳泓は「虚」を用いる
『太極』は「天地・万物の理に他ならない。天地について言えば、天地のなかに太極があり、万物について言えば、万物のなかにもおのおの太極がある」10e)というように、『太極』は『理』との解釈である。
張載は『太虚即気』を論じた。「つまり〈太虚〉は「気」だとして、虚無・空無を否定し、気が藂まると〈万物〉となり、気が散じると〈太虚〉となると考えた」9d)といわれる。また、張載は「『太虚』を不生不滅とし、聚散(生死)を『客形』*として捉え」127a)、「天地閒には氣という實在物が充滿してをり、・・・太虚と物との兩様の循環を繰り返す、永遠の循環運動の中にある」(気の運動によって萬物の消長、宇宙の運行を説明する)128a)、「生エネルギーの場」127b)であるとする。 *物として現れた姿
しかしながら、『道』と『太虚』・『虚霩』の関係として『淮南子』(天文訓)「天墬の未だ形あらざるとき、馮馮翼翼、洞洞屬屬たり。故に太始と曰う。太始は虚霩を生じ、虚霩は宇宙を生じ、宇宙は氣を生ず(天地未形の馮翼たる状態は太昭(始)と称するが、それは道にほかならず、その道から虚霩を生じ、虚霩から宇宙を生じた)」28e), 129a)を三浦国雄 氏は「『天下の万物は有用より生じ、有は無より生ず』という老子流の生成論を形象化したもの」127c)であり、「虚霩を太虚と読み換えうるとしたなら、天地万物の始源という時間的な奥行きをもつことになる(一部略)』127c)と論じている。
ここで『太極』と『太虚』との違いをみると『太極』の生成論は、「太極-両儀-四象-八卦であれ、太極-陰陽-五行-万物であれ、『一』なる『太極』の『多』への一方的な流出と捉えられ」127d)、『太虚』は「『太虚』を基地とした往還であり、万物は『太虚』から出て『太虚』に帰る」127d)、すなわち「太虚→(聚)→物→(散)→太虚」128a)である。
気論としては「太極型が陰陽の気の交感という男女モデルの生成を説くのに対し、太虚型は気の聚散という、呼吸モデルに基礎を置く(略)」127d)とする。なお、『関伊子』では「『太虚』が気を生むのではなく、太虚即気であって、両者はただ体(太虚)と用(気)という、存在の相において分けられるべきものであった」127a)とされる。
『太虚』に『理』はあるのか?大島 晃 氏の「『太虚』の性格を考えるとき、朱子に於ける『理』的なのもが、すでにそこに含まれていると言えよう」128b)(『朱子語類』*1「太虚即氣の太虚とは何のことですか」「理のことである」)128b)とするところから、『太虚』に『理』をみる。故に『太虚』とは無限の宇宙*2空間127e)(天)であり、すじみちとしての理9e)を含み、気が聚まり萬物を生み、散じて虚に還る概念とするのが《柳泓の思想に適う》と愚生は考える。
*1朱子語類.巻九十九、第十三條(鄭可學の錄)128b)、*2宇宙:宇は四方上下の空間的なひろがり、宙は古くから今に至る無限の時間をいう129a)
〈氣の思想〉について
『気』をここで語りつくすことはできない。終わりなき哲学対象である。
「道は人間の心にも宿るが、心だけでなくて、『気』あるいは形にも宿ることがいわれ、また、神は人間の心にも宿るが、心だけでなくて、身にも宿ることがいわれ、一方、『気』は人間の身にも宿るが、身だけでなく、心にも宿ることがいわれる」9f)。
道家の気の論には「世界の始まり、天地開闢と万物の生成を『気』によって説明する宇宙生成論的なそれと、人間がどのようにして自己の生を全うしうるかの英知を『気』によって説明する養生もしくは養性論的なそれとの二つに分かれる(一部略)」9g)とあるが(究極的には一体のものである)、ここでは宇宙生成論における『気』を考えたい。『道』から始まる『気』の位置づけと役割を時の流れとともにザックリみていこう。
『老子』の「道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生ず。万物は陰を負うて陽を抱き、沖気以て和を為す」9g)は前述したように、「道から万物の生成するプロセスを陰陽二気の冲和で説明したもの」9g)で、「道」は「一」の上位の概念であり、気は「道」より生まれ、「一」は「一気」、「二」は陰陽の二気、「三」は陰陽二気と冲気とを合わせたものと解釈されうる8c)。「有」とは「気」である8c)。つまり、「(一)気」はあらゆるものを生み出す始原である。
『荘子』の(天地篇)「泰初に無有り、有ること無く名無し。一の起こるところ、一有るも未だ形有らず・・・」、あるいは(斉物論篇)「以て未だ始めより物有らずと為す者有・・・其の次は以て物有りと為す」などは、「『道』は『一』の上位概念となって、後世の『理』すなわち形而上の世界〔道〕と『氣』すなわち形而下の世界〔一気〕とを区別して考える理気二元論の展開へとつながる(概略)」9g)とされる。
しかし、荘子は妻の死に際して、「其の始めを察して本と生無し。徒に生無きのみに非ざるなり。而うして本と形無し。徒形無きのみに非ざるなり。而うして本と気無し。芒忽の間に雑り、変じて気有り。気変じて形有り。形変じて生有り。今ま又た変じて死に之く(もともと生命などなかったのだ。いや、形などというものもなかったのだ。いや、もともと気— 万物を形づくる元素、陰陽の気— もなかったのだ。・・・ぼんやりとして定からぬ渾沌のなかで一切が無秩序にまじりあっていたのが、次第に変化して気(陰陽の気)となり、気が変化して形となり、形が変化して生命が生じた。ところが今また生命が変化して死— 本来の混沌— に帰ってゆく。そして、このような混沌→気→形→生→死(混沌)の変化こそ相互に一連のものとして、春夏秋冬の四季の移り変りのように規則正しく循環してゆく(一部略))」75f)と語る事物とその変化をみるに、‟「気」一元論的”として解釈8c)しうるとする。
『淮南子』(天文訓)の「道は一に始まる(道於始一)」は「道」と「一(太極:太一)」を同位の概念9g)とし、その生成論は「気」の一元論であるとする8c)。一方、「道—虚霩―宇宙―気―天地―万物」9h)という生成過程も説き、「道」を「気」の上位とする9i)記述もある。
『河上公注』(第一章)においては「気を吐き、虚無より出で、天地の本始と為る」9h)とあり、「道の吐出した気は天地の間に包含され、そこに万物の生成が行われるという。この道―気-天地―万物という生成の過程は『淮南子』の生成論をふまえたもの(一部略)」9h)といわれる。
隋唐・五大に至ると「万物を形成すると考えられた水木金火土の『五行』は、それだけでは単なる物質、もしくは五つの元素であるが、陰陽思想との交渉過程において、それが人事や自然を動かす力と考えられるようになると、五行の一々に気が配当して説かれるようになった」9j)ようだ。
宋学の創始者の周敦頤は「太極圖説」<太極→陰陽→五行→万物化生>により、「万物を化生するにあたっては、太極・陰陽・五行の三者が互いに作用しあって万物を生じる(『太極』は気と考えていたと推測される)」9e) とした。その後、朱熹(朱子)は「太極を理、陰陽を気、五行を質であるとし」9e)、程頤の<理気二元論>、張載の<気を万物の物質的根源とする(万物の生滅を気の藂散による)>説を、周敦頤の<陰陽に五行を組み合わせて万物の成立を考える>点を取り入れ、理気哲学の理論体系を完成させた9e)。『太極』は天地・万物の『理』である10e)。陽を生ずるのも陰を生ずるのも理である。「陰陽は『気』で、この二気が分かれて五行になる。五行は質だが、五行の気があるから物を造れる(略)」10e, f)と説く。
ニーダムは、『氣』=物質=エネルギーと捉えている:「(張載の)氣の集合による物質の形成という概念(氣積爲質)」は朱熹によって受け継がれたとしている11d)。そして、「氣」が凝結して物質を形成する過程を陰とし、その拡散の過程を陽とし11d)氣と陰陽が結びついた。ニーダムは『朱子全書』(巻49:理氣一.総論)の「天地之間 有理有氣 理也者 形而上之道也 生物之本也 氣也者 形而下之器也 生物之具也 是以人物之生 必稟此理 然後有性 必稟此氣 然後有形:天地を通じて理が存在し、また氣が存在する。理は上からあらゆる形態(形而上)を(組織する)『道』であり、あらゆるものが生まれてくる根本である。氣は下からあらゆる形態(形而下)をつくっている器具(器)であり、あらゆるものがつくられる道具であり原料(具)である・・・」11e)から、「明らかに『氣』を物質=エネルギーとして、また『理』を宇宙組織の原理として解釈することを正当化している」11e)と述べている。
三浦国雄 氏も「気はこの宇宙に充満するガス状の連続物質。物を形造る基本物質であるが、同時に生命・活力の根源であって、正確には物質=エネルギーというべきであろう」10d)と現代的な解釈をしている。
三浦梅園(1723-1789)は気物の「天地かくの如く紛々擾々として、物多き様に見え候へども、只かたちある物ひとつ、かたちなき物ひとつ、此外に何も物なく候。其のかたち有物を物と申し、かたちなき物を氣と申候」と明快である130a)。
一気について・・気と被るが
『気』を一なるものとして、その聚散によって萬物の生成変化を生じるか、陰陽の『二気』の交わりによって萬物の化生が行われるのか。
福永氏は、『荘子』は「『一気』という概念を明確に用い、人間を含む万物の生滅変化を『気』の集散離合で原理的に説明した」9g)として、以下の文を挙げている。『荘子』(知北遊篇)「生也死之徒 死也生之始 孰知二其紀一 人之生氣之聚也 聚則爲レ生 散則爲レ死 若死生爲レ徒 吾又何患 故萬物一也 是其所レ美者爲二神奇一 其所レ惡者爲二臭腐一 臭腐復化爲二神奇一 神奇復化爲二臭腐一 故曰 通二天下一一氣(天地一氣の誤写?)12c)耳 聖人故貴レ一」4e),12c)。これについて「生は死の同類、死は生の始めともいえるのであって、何びともその根本のけじめを明らかにすることはできないのである。というのが、人間の生命は「気」すなわち天地宇宙の間に遍満し、一切万物を一切万物として成り立たせる原素が集合することによって出来あがったものであり、この気が集合すれば生、離散すると死になる。今もし生と死の現象が同じ気の離散集合にすぎない同類一体のものであるとするならば、万物の生滅は天地の一気の在り方の変化にすぎないということになり、我々は何も死生の問題に心を苦しめることはなくなるであろう。かくて万物はみな天地の一気によって形づくられていることになり、この点から言えば万物は根源的には一つなのである」12c)と説く。
『荘子』(大宗師篇)の人間の生死を語るなかで「天地の一気に遊ばんとす(而遊乎天地之一氣)」6c)について福永 氏は「一切万物がそれによって生滅変化する宇宙的原質—「気」」6c)として、池田 氏は「天下の一気」を「気は一なるものであって、その一気の聚散が万物の生成変化である」8e)とし、松村 氏は「多様に変化する事物の本源」8c)と解釈している。
また、無為自然の哲学における基本的な概念の『徳』と「一気」について「泰初に無有り。有ること無く名無し。一の起こるところ、一有るも未だ形あらずして、物の得て以て生ずる、之を徳と謂う」131a)を、福永 氏は「道(無)から『一』が生じる、すなわち天地に遍満し、一切万物を一切万物として形成する原質であるところの一気が生起する。しかし、このようにして生起した一気は『一ありて未だ形にあらず』―― 渾然たるカーオスとしての一つの全体をなして存在しているにすぎず、そこにはまだ万物の形はあらわれていないのである。そして『物の得て以て生ずる、之を徳と謂う』―― 万物はそれぞれにこの一気を得ることによって形をもつものとなり生成してゆくのであるが、この場合、万物のそれぞれに得ている一気を徳とよぶのである」131a)と述べている。
おおよそ「一気」は以下にまとめられる。「気は物を形作る基本物質である、・・・物の生成と消滅にかかわるのはあくまで一気であるが、一気は陰陽の二気に分かれ、木・火・土・金・水の五行となり、万物を形成するから、気には一気・陰陽・五行というカテゴリーがある。一気が静ないし聚の状態にあるときに陰と呼び、動ないし散の状態にあるときに陽と名づける(抜粋)」10d)また、「万物はしかし、気だけによって構成されているのではない。一気から万物への生成展開は、同時に太極が万物に具在する過程であって、かくて万物の個々に内在した太極は理と呼ばれる。従って、存在は理と気によって構成されている」10d)と。
天地とは そして理念とは
柳泓の「天地ハ何ニ物ゾヤ。天地は一気也。天ハ即チ太虚ニシテ、地ヲ離ル、以上ハ皆天地也」1t)とは。次の問に「日月ハ何ニ物ゾヤ」1t)、「星宿ハ何物ゾヤ」1t)と出てくることから、『天』はそれより上位の天≒宇宙を示していると思われる。ここでいう『天地』は天と地の間を指していると推定される。天地は「一気」、万物の生成と消滅を行う場と考え、『天』は『太虚』すなわち、地より上にある空間であり、これが天地である、と読むが。。。先人の三浦梅園は「天地とは、もと氣物の成名にして、氣天を成し物地を成す物に候へば、一物あれば一天地、萬物あれば萬天地也」130a)と申し候。
柳泓は「天地万物は皆一針眼の虚中に其理を含蔵して出来」1b)というように、『虚』に『理』があることを明言している。「一虚の中より天地・日月・星宿・水火・禽獣・虫魚・草木・人類まで変化し来る者なるべし」1f)。ここで『虚』と『太虚』は区別して考える必要がある。『天地』を生み出すのは〈一針眼の虚中〉、〈一虚の中より〉と『虚』をひとつの“点”として捉えている。一方『太虚(大虚)』は〈一気〉である。そして『天地』にある。
〈天ハ即チ太虚〉、あるいは〈太虚ハ一気ノ精キ者也〉1t)〈大虚*は一気にして天地の間に有て最精き者なり〉1f)、〈夫レ人太虚ノ中チニ在ツテ太虚ヲ見ザルコトハ、猶魚ノ水中ニ在ツテ水ヲ見ザルガ如シ〉1t)、〈俗人大虚を以て無物なりと思へるは・・・魚は水中に有て水をみず、反て大虚をみて以て有物とせり〉1f)より「太虚」は『天地』の間にあるものと理解される。さらにいうと「太虚」は地の上の「天」である(地ハ一気ノ粗キ者也)1t)。
*『理学秘訣』では『太虚』であるが、『心学奥の棧』では『大虚』(おおぞら)である。
これらを惟ると、『虚』とは(理)である。『虚』より『天地』が出で来るので、‟無名天地之始”:天地に先行し天地の万物の根源をなす『道』の位置づけ、となる。そのひとつ(点として)の『虚』より天地(大虚)が生まれ、『一気』である天地、すなわち太虚より萬物が生成する。「気ハ形アツテ実也、理ハ形無フシテ虚也」1u)というように「理」を無形の虚とする。
朱子学では『太極』は(理)で『陰陽』は(気)である。「太極」-「陰陽」-「五行」-「万物化生」いう流れ、柳泓はこれを用いない。『理気二元論』は思想の根底にあるものの、既述したように『五行』を否定して『三行』としていることからも、あえて張載の『太虚』を用いたとも考え得る。これは、『物』が存在しそこに条理(法則)をみる1u)、という自然科学の影響もあるのか。。。
ここで、柳泓の〈魚は水中にて水をみず・・・人亦気中に有て気をみず〉1a)は、司馬江漢『春波楼筆記』の「魚水に遊びて水を知らず、人気中に居て気を見ず」103c)、『和蘭天説』の「一壺ノ中ヲ小天地ニタトフ水火ハ人ノ視ル所ナレド氣トナリテハ不レ見魚ノ水中ニ遊デ其水ヲ不レ知ガ如シ」122c)からの着想か。
12.ひとつの起源から宇宙そして生命が生じた 宇宙~生命の連鎖
最も重要な言葉「一虚の中より天地・日月・星宿・水火・禽獣・虫魚・草木・人類まで変化し来る者なるべし」1f)
この論を釈く前に、司馬江漢は「夫ㇾ天地万物ノ造化ハ、是レ人間及ビ禽獣艸木虫魚ノ如キニ至ルマデ、皆悉ク天気之ヲ生育スル也、天ノ陽気、地気ニ徹シテ、万象生長スルノ所以ハ、人ト艸木ト咸ク同物ニシテ、核子地ニ墜ル時既ニ芽ヲ生シ、始メテ二葉ヲ出スハ、是人ノ産ルト理ヲ同フス、親ノ精気ハ即チ核子ナリ、母ノ胎内ヨリ産ルヽハ、彼ノ二葉ヲ生スルガ如シ」109k)、さらに「上天子将軍より下士農工商非人乞食に至るまで、皆以て人間なり、獅子、熊、狼、犬、猫に至るまで獣なり、人魚、鯨、鮫、鰯に至るまで魚なり、鸞、鳳、鴻、鴈、小雀に至るまで皆鳥なり、蛇、百足、蚯蚓に至るまで虫なり、小は大に逮はず、大は小を従ふ、是皆地球の水土に生ずる者にして各心あり」103d)と論じている。これを読むと、本論となる命題がすべて解き明かされそうにもなる。すなわち、生命体はひとつにつながっている、そして、それぞれの類は同じものの仲間に分類される、すなわち種の起源は同じであると。柳泓の思想の根幹として流れるものは司馬江漢であったのではないか、少なくともその影響は多大なるに違いないと。『理学秘訣』の「譬ヘバ卵ヲ空中ニ掛クルガ如シ。天文家ノ説是也」1t)の天文家は司馬江漢「大地ハ天ノ半ニ浮ミ係テ在ト雖・・・鷄卵ノ如シト云」109a)である。
さて、あるひとつの中(無限)から天地、太陽、月、星の宇宙が誕生して、水、火がつくられ、そしてある生命の源(細菌・アーキア・真核生物の最終共通祖先:LUCA132a)、コモノート133)など)*から植物、鳥や獣、魚、虫、人類に変化してきたのである。いわゆるインフレーション・ビッグバン説のような展開、―― 『虚から生じた宇宙の誕生、生命の発生、生物の変化までひとつにつながっている』、ということをこの時代に見抜いている。これこそは、鎌田柳泓が世界に先駆けたもっとも優れた哲学なのである。いうまでもなく、無から有が生まれ、理法に従い気によって変化を伴い世に現われる、元を辿れば虚に繋がる、つまりこれが『道』なのである(愚性)。
*LUCA、コモノートは地球の最初の生物ではない。
ボネ(1720-1793)は自然物の階梯として、はしごの一番上に人間(L’HO MME)、次にオラウータン、サル、「四足動物」の蘭、それ以降おおまかに鳥類、両生類、魚、貝、昆虫、植物、鉱物、元素(最後は水、空気、火)と下段に向かって書いている134a)。ヘルダーは『Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit:人類歴史哲学考』(1784)で「石から水晶(結晶)へ、水晶(結晶)から金属へ、これから草木へ(金属から植物世界へ)、植物から動物へ、動物から人間へと吾人(我々)は組織の形式の向上(有機体の形が上昇)するのをみた、之と共に又生物の氣力と本能とは複雑になり(被造物の諸力や本能も多様なものとなり)、而して結局すべては人間の形状に於いて包括せられ得る限り統一されうるのである(ついにはすべてが人間の形態の中に包括されうる範囲で一本化される)」92b), 135a)と、無生物から人間への発展をみている。しかし、これは先の「存在の連鎖」*と同様であり、宇宙からの始まりではない。西欧に限らず、世界のほとんどは神話・伝説による宇宙の誕生、そして人類の誕生論である。 *(中)9.に記載
神や全能が関与しない、あるひとつの中から、宇宙が誕生して生命とつながり、その生命の起源も、多様な生物もそのひとつを起源として出てきてきた、という、西欧では示されてこなかった起源論である。この時代まで生き物が一つの起源であり、かつ宇宙の起源と同じ(繋がる)ものであることを記した書は愚輩が知るかぎりでは、東洋の書のみである。
『老子』(道徳經)の「道可レ道非二常道一 名可レ名非二常名一 無レ名 天地之始 有レ名 萬物之母 故常無欲三以觀二其妙一 常有欲三以觀二其徼一 此兩者同出而異レ名 同謂二之玄一 玄之又玄 衆妙之門」(體道第一)125a)「道の道とすべきは常の道に非ず。名の名とすべきは常の名に非ず。無名は天地の始めにして、有名は万物の母なり。故に常に無欲にして以て其の妙を觀、常に有欲にして以て其の徼を観る。此の両者は同出にして名を異にするも、同じく之を玄と謂ふ。玄の又玄、衆妙の門なり」136a)について、阿部吉雄・山本敏夫 氏の通釈より「(此兩者以下)天地と万物、この両者は、共に同じ所から出ている。すなわち天地は同じ一つの道から、万物は天地という同じ親から。ところが同じ一つの道から出ながら、天と地というように名を異にしているし、また天地という同じ親から出ながら万物はそれぞれ名を異にしている。このように同じ所から異なったものを産み出している不思議な働きをしているもの、これを玄という。この奥深いかすかな所、これがさまざまな微妙な現象を産み出す門なのである」125a)とされる。また、『淮南子』(原道)の「萬物之總 皆閲二一孔一 百事之根 皆出二一門一(萬物の總は皆一孔に閲り百事の根は皆一門より出づ)28g):万物の全体はみな一つの穴(孔)によって統括され、万事の根源は全て一つの門に由来する」137a)は、まさしく現代の宇宙・生命起源論のようでもある。まあ、このような素養も〈一虚の中より〉を連想させているのかもしれない。しかし、『孔』は無から生み出されたのか、もとものとある無の『孔』であるのか。ワームホールもちらついて悩むところである。
あるひとつの起源が宇宙から生命までを創る、すなわち、かたちを変えているだけであり、おなじものなのである ―― これは、中村 昇 氏が語るホワイトヘッドの「神は一切の創造に先立つのではなく、一切の創造とともにある。・・・神は、世界に満ちている『目的論的生命』といいかえられるかもしれない。神は、創造活動という無目的なエネルギー状態(「場」)に『形』をあたえ具体的なものにし、世界全体を目的をもった生命体にする」138a)という観念、そして「すべての現象は生命である、宇宙はすべてが複雑にからまりとどまることのない関係そのものの流動体である。つまり、この世界の存在は、ことごとく生きている(この状態を有機体という)、この世(宇宙・現象・時間)は〔非連続的な連続〕である(一部改)」138b) 、という思想にもつながるところがあると、勝手に思うのだが。
柳泓は「一虚の中より天地・日月・星宿・水火・禽獣・虫魚・草木・人類まで変化し来る者なるべし」1f)と記している。草木、虫魚、禽獣、人類であれば連鎖としてスマートであるが、柳泓はなぜ人類に近い禽獣を横に並べずに〈草木・人類〉という順にしたのだろうか(虫魚・人物1m)の文もあるが)。ささいなことではあるが、気になる。「人身の如きも其初唯禽獣胎中より展転変化して生じ来るものなるべし」1f)という〈禽獣から人類〉の出現は、『荘子』(至楽篇)に記載されている〈馬は人を生じ〉4d), 75b)から導かれたと先に推測した。しかし、草木・人類というつながりは生物の連鎖として妙である。『朱子語類』に「只此氣凝聚處 理便在其中 且如天地間 人物草木禽獣 其生也莫不有種(気が凝集した時、理はその中に存在する。たとえば天地間の人物・草木・禽獣は、それらが生まれるには、みな種がある)」119b)、にみられなくもないが。しいていうなれば、荘子の【萬物斉同】(人間が絶対者となるためには、一切存在が要するにみな究極的に一つである立場に立たなければならない)6d)という理念、つまり、生きる物には上も下もない「あらゆる対立と差別とを越えて、一切をそのままに包容し、肯定する無限者たれ」136b)、「萬物蓋然 而以ㇾ是相蘊」125e)の精神を宿している、伊藤仁斎『仁斎日札』の「人与二草木一同生ル、亦当下与二草木一同腐上:人は草木と同じく生える。また当に草木と同じく腐るべし」139a)である。そしてやはり、司馬江漢の「天地万物ノ造化ハ・・・人ト艸木ト咸ク同物ニシテ」109k)の"人ト草木ト咸ク同物"という言葉が無意識のうちに<草木・人類>へと作用しているのでは、と思ってしまう。
時間の概念 話は変わって、八杉龍一氏は『理学秘訣』や『心学奥の桟』の「記述全体から見てそのもとヨーロッパから伝来した知識にあることがほとんど明らかだ」140a)と述べられているが、これまでみてきてのとおり拙者の見立てでは、そのほとんどは中国からの思想(哲学)であり、儒・道・沸の三教一致を中心教義として主に『太極圖説』・『通書』・『易』・『樂記』を尊重していた5d)というところからも、老・荘思想、特に儒教(学)の思想を基本として論述されていると考えられる。進化に関しての端緒となる論は大昔より中国の書に記されており、八杉氏が「その思想は直接的には、(祖父)エラズマス・ダーウィン、ラマルク、あるいは他の先駆者から蘭医書を通じてはいったことが、まず考えられる。だがそれと思われる蘭書は発見されていないという」57b)と書いているように、無いに等しい。愚輩もいろいろ蘭書を探したが見つからない。少なくとも柳泓がそれ(西欧の進化思想)を基に記したのではないと断言できる。ただし、西欧の科学に造詣の深い、特に司馬江漢✝の慧眼ともいうべき‘識’に感化されて、宇宙、自然、生命そして進化を思案するに至ったことは否定できない。 ✝キーパーソンと考える
八杉 氏は「ヨーロッパでの進化観念が時間の拡大の観念と結合している」140a)として、進化思想には「時間の観念」が重要であると指摘している点についても考察してみたい(チャールズ・ダーウィンは、生物の進化には長大な時間を要すると考えていた(わずかな変異の長年の累積によって大きな変化となる)72b)。
中国における天地開闢について『三五暦記』(3世紀)に「未だ天地あらざるの時、混沌として、状雞子(卵)のごとし。盤古(巨人)その中に生ず。一万八千歳にして天地の開闢するや、清陽なるもの天となり、濁陰なるものは地となり、盤古はその中にあり」129b)という神話がある。これを踏まえてか、『朱子語類』(1263、1270刊刻)には「問自開闢以來。至今末萬年。不知已前如何。曰。已前亦須如此一番明白來(天地開闢より今に至るまで、まだ万年もたっておりませんが、その前はどうなっていたのですか。その前も、きっと今みたいにはっきりした世界があったはずだ)」10g), 119a)とあり、この世界は【万年も前からあった】と、西欧よりも遥か以前から進化思想を妨げる時間的なしばりは無かった。ものの進化・変化を為すのに十分な時間があった、むしろ、ものが変化しうる化生の論には、時間的な制約を考える必要もない、といのが基本的な観念と思われる(しかし(上)で記した『淮南子』(墬形訓)28a)の例はある)。もちろん、この時代に『日本書紀』の建国がこの世の始まりと信じていたとは思われない。柳泓の『気』によって万物が変化しうる時間的な概念は不明であるが、「燕の卵は蛇の気に感じて蛇となりたるなるべし」1v)、あるいは八杉氏が示した『理学秘訣』の「天地・日月・山野・江海ハ無窮ノ寿也。人寿ヲモテ是レニ比スレバ、弾指ノ頃ノ如ク、電光石火ノ如シ」1w)、そして『荘子』にズバリ示される「物之生也 若驟若馳 無動而不變 無時而不移」(万物の生成変化は、その迅速なること馬の驟せ馳けるがごとく、一瞬一瞬の動きのなかで不断に変化し、一刻一刻の時間とともに絶えず推移していく」75d)のような筆から、『化生』は瞬時にもなしうると考えていたようにも思われる(エラズマス、ラマルクらの説とは全く異なる時間的観念である)。
一方、西欧の18世紀から著された地球の年代説をみると、ド・マイエ(1659-1738)は「もし、レンガやテラコッタの破片が海から1,200フィート上がった採石場で発見されたなら、その海水が一般的な尺度で1世紀につき3インチ減少すると仮定すると、この場所にはおよ そ50万年前に人が住んでいたことがわかるだろう(おきな訳):si on trouvoit des morceaux de brique ou de terre cuite dans des carriéres éleveés au-dessus de la mer de douze cens pieds, en supposant la mesure commune de la diminution de ses eaux à trois pouces par siécle, on sçauroit que la est habitée par les hommes il y a près de cinq cens mille ans,」(1748刊)88b)と記した。Gribbinは「Telliamed estimated that the Earth is billions of years old141a):テリアメドことド・マイエは、地球の年齢を数十億年と推定した13c)」と書いているが、1748年刊の原文(第2巻)88)にはこの記載がない。菅谷 暁 氏の訳書『自然の諸時期』の中で「ブノワ・ド・マイエの地球史は基本的に海水中の低下の歴史であり、・・・海水準の低下は100年で約三プスと見積もられているので、数千メートの山を覆っていた水が現在の水準まで低下するためには数百万年が必要である」142a)との解説を考えると、Gribbinは単位を間違えた可能性がある。その他、ビュフォンは地球が冷えて現在の温度になるのに74832年(月は16409年)143a)、「トーマス・ライト(1711-1804)は宇宙の回転に100万年以上、カント(1724-1804)は現在の宇宙が完成するのに数百万年から数億年(一部略)」142b)という考えを示している。しかし、このような時間軸は例外として、西欧世界の起源はJacob Usserio『Annales vesteris testamenti, a prima mundi origine deducti』(1650)に記載の万物創成から現在まで6000年「IN PRINCIPIO creavit DEUS Cœlum & Terram. [Geneʃ. I. I ] quod temporis principium(juxta nostrum Chronologiam)incidit in noctis illius initium, quæ XXIII. Diem Octobris præcessit, in anno Periodi Julianæ 710.(不明文字あり):初めに神は天と地を創造した。時間の始まりはユリウス暦710年10月23日(紀元前4004年)♰」144)である。この世界起源は東洋の歴史概念よりも短く、固定化されたものである。 ♰‘おきな’訳
西欧において、本当に必要なことはキリスト教神学の6000年を科学的根拠をもとに誰かが変えてくれることである。強固な牙城を一か所でも崩してくれる分野があれば、それに続くことができる。そうでなければ、全能のもとに隠蔽されてしまい、進化論の出る幕はない。その意味では、地質学の『斉一説』(uniformitarianism)によって地球年代6000年を破壊したハットン(1726-1797)、その後のライエル(1797-1875)の功績(紆余曲折はあるが)は大きい112b), 145a)。「起源についての3つの哲学的大問題、世界の起源、生命の起源、人類の起源はすべて聖書からもぎ取られて地質学の対象とされた。世界の歴史を書き直すに当たっての地質学の勝利は、時間についての偏見が打破されたということを意味していた」145a)とあるように、ようやく地球の歴史年代に新たな楔が打ち込まれることになった。
13. 鎌田柳泓の「進化思想」についての総括 ⊶ 進化を説いた ⊶
ここまで柳泓の根幹となる思想をみてきた。もう一度、振り返りながらこれまでとは違う視点で読み解くことができるかもしれない。先述してきた論との齟齬もありうるが書き留めよう。
鎌田柳泓はなぜ生物みな一種よりして散じて万種となると考えたのか?
①松は多様性に富み、同じ種でも別な形態の松がある。
②アサガオは人為的に劇的な変異が作出される。
③洋犬と和犬の交雑は親の形質が混在して現れる。
松は地域で形状の異なる松がある(形態的種)、アサガオは人為的手法により形質(形状・形態)の全く異なる様々な品種を作り出した(品種改良:便宜的に‘品種’という言葉を用いる)。また、動物も犬の和種と洋種の交雑から親とは異なる形質の犬(半犬)が生まれる。これらから推察するに、生育環境や交雑により多様な形質をもつ動植物を生み出すことができる。それゆえ各々の種は元をたどれば一つであり、共通の祖先から分岐し多様な新しい種が広がったと思考したと解する。
柳泓の論は〈土地の異なるによりて変化して種々の形状をなす〉〈有情の類、禽獣・魚鼈・昆虫の類もみな異類互に相交接して無量の形状・性情を変化し出し来るなるべし〉であり、『環境変異』による形質変化と『異類の交接』が種の分化の理論である。環境要因が生物に変化を与える、また異類交接によって万類は変化をともない生まれるのである。
論点を整理すると、非情と有情がある。ここでの非情は植物(草木)、有情は動物(禽獣・魚鼈・昆虫など)である。生物の変化は二つある。ひとつは環境であり、もうひとつは交雑である。
柳泓の哲学思考の根幹は、朱子学の『二氣交感、萬物化生』である。すなわち陰陽の気の交わりにより新たな物が生み出される、その後も様々に変化して物が生まれてくる、という思想である。しかし、天地は『太虚』、太虚は『一気』として記しているように、張載の『太虚即気』の「一気の聚散による萬物の生成変化」8e)という概念(氣、聚れば、則ち離明、施すを得て形有り。氣、聚らざれば、則ち離明、施すを得ずして形無し(離明:目にみえること))128c)も持ち合わせ、二気相交による生成のみを信奉していなかった(12.燕の卵は蛇の気に感じて蛇となる1v)より)。
まず、非情である。これまで述べたように、柳泓の時代に草木の雌雄、すなわち交雑は知られていない。そこで交わりによらない化生を考える必要がある。なぜ同じ種類で多くの異なるものが存在しているのか。『松』(木本)と『アサガオ』(草本)を例としている。『松』は『アサガオ』と違って多年生である。アサガオのように化して生成されてくる品種を目にすることはできない。そこで『松』は生育している土地によって違いがあることを思い浮かべる。その土地にその形質(形状)の木があるのは、そこの気候、土壌などの影響を受けて形態が変化した、という推測である。ここの議論は、ひとつのものからどのようにして変化したかである。蝦夷松が杉の葉に似ているのは、寒さという温度条件が葉に影響を及ぼして形状を変化させたのだ。しかし、その形が寒地に適しているとは述べていない。なぜなら杉が寒い地方に生息する樹種ではないからである(蝦夷には杉が自生していなかった)32d)。((上)では適応と選択を推察したが)。また、同一の種類の松でも生育地によって形状が異なっている。それはその地域の環境による影響を受けているからであると。ここで述べているのは、環境条件が生物に変化を及ぼすという、因果的な説明である。例えば風が吹くところでは曲がった木の形状となり、土壌のpHによって花弁の色も変化する、という『環境変異』である。ここでの論旨は形態変化に及ぶす要因は「環境条件」(気候、光、水、土壌等)、すなわち理化学的な力(作用)なのだということである。この発想は『理気』にある。天地にある「理」が「気」に作用して変化を生み出すのである。その『理気』が『環境』である。ここに「気」によって変化したと記されていたら、もはや議論は終了である。
続いて松は一つの種から異なる形状を生み出している、とすれば蝦夷松の葉と似る杉、同様な葉の槇、さらにいえば類似な葉形のものは松と近縁、いや松に由来しているはずだ、と閃く。形質(形態・形状)は変化する、同じ種から異型が出現する、類似の形状は同じ起源をもつという類推、そして、ひとつの起源から種が分化する ―― という結論に達する。これは『老子』(四十二章)を知っているものであれば容易に導かれる。
一方、『アサガオ』は、百花繚乱・千紫万紅の品種が続々誕生している。『交雑』によることは言及されていないが、〈種々の花葉を変出し〉という言葉から〔何らかの人の手による技〕が変化の要因と考えている。ともあれ、種を超えるような仰天の形状を生み出すことができるという現実を知り、ということはこれまでも世に出でてきたという推論が成り立つ。これをもって〈所有千草万木みな一種の植物より変化し出せり〉と推量する。
有情の類について。例えば、犬の「唐犬」と「和犬」の交雑から「半犬」となる。片方の親と全く同じものが生まれてこない、いろいろな形質が混在して現れてくる。すなわち、異なるものが出現する。『交雑』は、種の分化を生み出すことができるひとつの方法であることを記している。これは、『陰陽二氣交感、萬物化生』に合致する。有情の類には雌雄があり、交雑することを知っている。そこで〈有情の類、禽獣・魚鼈・昆虫の類もみな異類互に相交接して無量の形状・性情を変化し出し来るなるべし〉と記す。ここに、草木の一なるものからの出現を有情の類にも当てはめて、〈生物有情非情ともにみな一種よりして散じて万種となる者なるべし〉として読み解き、そして天を仰ぐのである。萬物化生、二気交感、陰陽、一気・太虚...理・虚 無=道と。
生物は環境、交雑により形状の変化を為す、これら現象の推考よりすべての生物種はひとつの祖先から派生して多様性を生み出してきたことを世に提示したのである。ここには、既述してきたように西欧の進化の情報から着想したと考えられるものはない(当時の西欧は、種の不変論とデザイン論72a)により新たな種は生まれないとされてもいた)。これまでみてきたように【気によって萬物の化生が行われる】東洋思想の基盤の上に成り立っていることは明らかである。
この「生物有情非情ともにみな一種よりして散じて万種となる者なるべし。猶又其至りを論ぜば唯一虚の中より天地・日月・星宿・水火・禽獣・虫魚・草木・人類まで変化し来る者なるべし」1f)は、鎌田柳泓のオリジナルである。
鎌田柳泓は、もっとも基本的ないわゆる進化論の骨格となる構想『祖先種からの分化によって新しい種が生まれる<種は変化する>』ことを明言した事実は消えない。しかし、「実証的考察の乏しさ」146a)と指摘されるように、なぜ共通の祖先から分岐して種が形成されるのか、どのようにそれが形成されたのか、もう一歩踏み出したメカニズムの論考・論証が欠けているのである。
チャールズ・ダーウィンが述べた「種は單獨に創造されたものでなく變種(variety)と同様に他の種から出たものであると云ふ結論に達するのは決して想像され得ないことでない。けれども、このやうな決論は、たとへ充分な根據があっても、この世界に存在する無數の種が、實に驚くべき完全な構造と適應とを得るまでに、どうして變化して來たかと云ふことを説明するのでなかつたならば不滿足であることを免れない」147)。言い方を変えると、「すべての種が別々に創造されたものでなく、共通の祖先から進化によって導かれたことを示すためには、すべての種がなぜその生活環境に驚くほど適応するに至ったかが説明できなければ不十分である」148a)。原文「In considering the Origin of Species, it is quite conceivable that a naturalist, reflecting on the mutual affinities of organic beings, on their embryological relations, their geographical distribution, geological succession, and other such facts, might come to the conclusion that each species had not been independently created, but had descended, like varieties, from other species. Nevertheless, such a conclusion, even if well founded, would be unsatisfactory, until it could be shown how the innumerable species inhabiting this world have been modified, so as to acquire that perfection of structure and coadaptation which most justly excites our admiration.」149a)。Gouldによれば、「ダーウィンは『私は二つの異なる目的を念頭においている。第一に、種は個々別々に創造されたのではないことを示し、第二に、自然選択が変化を生みだす主要な原因であったことを示すことである』」150a)と記しているという。この第二の目標、すなわち進化機構の理論150a)が必要なのである。
補足:チャールズ・ダーウィンの進化論の骨子151a)
①共通の祖先から分岐して新しい種が生成される
②自然選択説(有利な変異が保存され、不利な変異は排除される)
(1)すべての動植物は親の数より生まれてくる子供の数のほうが多い。(2)それにもかかわらず、ほとんどの集団の大きさはほぼ一定している。(3)自然集団には非常に多くの変異がみられ、そのなかのある部分は遺伝する152a)。
進化の定義
『進化』の定義は独断で『岩波 生物学辞典』によることとした。しかしながら、第1版から版を重ねるうちに定義が、進化ではなく変化、すなわちゴールが変わっていく。2013年第5版では「生物個体あるいは生物集団の伝達的性質の累積的変化。どのレベルで生じる累積的変化を進化とみなすかについては意見が分かれる。種あるいはそれより高次レベルの変化だけを進化とみなす意見があるが、一般的には集団内の変化や集団・種以上の主に遺伝的な性質の変化を進化と呼ぶ」153a)。これでは、かつての進化の議論ができない。そのため、1960年第1版第1刷の『進化』の定義「生物の種ならびにさらに上位の各類が、過去から現在にわたって不変のものでなく、次第に変化してきたものであるということ。一般にはそれと関連して、生物がもともと一元のものであり、次第に分岐してそれぞれの種類を生じたという認識が含まれる」154a)を用いる。この定義にあてはめると、鎌田柳泓は『進化を説いた』と言える。異論はないはずである。
『進化論』の定義として「生物が進化したものであることの提唱、あるいは進化に関する諸種の研究および議論、またはそのうちとくに進化の要因論」とある154b)・・・ウーム。進化の提唱、議論はしているが、要因論が希薄である。『鎌田柳泓の進化論』に至らなかったのは致し方ない。
最後に。進化という点に着目してその背景と意図を思うままに推論してきたが、「柳泓の『理学秘訣』や『心学奥の桟』は、今日その内容が如何ほど高く評価されようとも、かれの本来意図したところは心学であり、それを措いてはその意義をじゅうぶん理解しえないものであることが結論される」1x)と『石門心学』の解説に記されている。・・・、柳泓は【すべてのものはひとつでつながっている】ことを世に訴えたかったのは相違ない。— 進化思想の原点は東洋にあり —
挿話:レオナルド・ボナパルドの講義を長崎で受けたとされる秋田孝季、和田長三郎吉次らの『東日流六郡誌絵巻』に宇宙生誕として「一塊より大爆烈起り、・・・」(寛政丁巳:1797)155a)、万物創誕として「生命の起これるは、三十億年歳前といふなり・・・種の類を万物に異らしめ、海中生々より陸にぞ寄りたるは、藻より草木となれる万物なり・・・人間の初めなる始祖ぞ、ネズミなりといふ。・・・紅毛人ダウイン説」(寛政戊午:1798)155b)、また『丑寅日本紀』に「万物生々進化之事」として「その生種より治水光熱の候に依りて、一種より二種へと分岐進化をせるに至りぬ・・・ダウエン博士に依れる生生万物進化論に於いては、すべからく実証ありて信じて惑わざる論証なり」(寛政五年七月廿日:1793)156a)と記された書物も話題となったようだが。
種あるいはその上位の類の壁を経験するならば、現在の進化はありえないと思うのである。連続的な分断。起源は一つではなく複数あるのか。何かにより爆発的な分散が生じたのか。蠢く染色体を眺めると生命の探求はこれからも続き、新たな進化の説が生まれることは間違いない。
・・・長くなった。ここまで長いとは。もし、飽きもせずに読破された方がおられたらなら稀有な人物である。地球外の生命体と呼ばれていらっしゃるのでは?いや、創造主として崇められておられるのか。すくなくとも、我が国に最後まで読み遂げられるヒトはいないであろう。~ おきな~
鎌田柳泓『心学奥の桟』(1818-1822)は進化を語るのか?(上)へ行く
鎌田柳泓『心学奥の桟』(1818-1822)は進化を語るのか?(中)へ行く
地獄なし極楽もなし我もなし たゞ有ものは人と万物
神仏化物もなし世の中に奇妙 ふしぎのことは猶なし 山片蟠桃『夢之代』118e)
アイキャッチ画像
『心学奥の桟(上巻: 挿絵. p. 9)』(鎌田柳泓. 1822)を基に一部創作した。
座敷でキセルを吸っているのは人間に数学を授けたマヤのゼロ神である。扇子を持っているのは柳泓らしき人物と思われる。黄色朝顔を掲げているのは歌人のようである。植木職人が差し出している鉢には黒チューリップが活けてある。女が持ち帰る鉢には真の青いバラが咲いている(フィクション)。
花の図柄参考:ユリ:木村洋次郎・大場秀章.シーボルト『フローラ・ヤポニカ』 日本植物誌【新版】.13-1 シロカノコユリ.p. 20.八坂書房.2023.花菖蒲:安藤広重「堀切花菖蒲」より.
鉢の図柄参考:国立歴史民俗博物館.伝統の朝顔 Ⅲ ―作り手の世界―.岩渕令治.1 江戸の園芸文化の発達.参考 歌川芳藤 草花植木つくし.p. 8.国立歴史民俗博物館.2000.
引用・参考文献(鎌田柳泓『心学奥の棧』(上)、(中)の一部を含む)
1)鎌田柳泓.心学奥の棧(1822)、理學秘訣(1816)を基に以下から引用:石門心學.日本思想大系42.柴田 実 校注者.岩波書店.1971.1a)心学奥の桟 上之巻 .p. 412、1b)同.pp. 410-411.頭注、1c)理学秘訣.p. 378、1d)解説.p. 454、1e)心学奥の桟 上之巻 .(逸話)pp. 410-411、1f)同.pp. 411-412 、1g)同.p. 411.頭注、1h)理学秘訣.pp. 383-387、1i)同.p. 385、1j)解説.pp.501-502、1k)理学秘訣.p. 387、1l)心学奥の桟 上之巻.p. 415、同.頭注、1m)同.p. 416、1n)理学秘訣.pp.381-383、p. 382 頭注、1o)同.p.396、1p) 心学奥の桟 上之巻.pp. 414-415、1q) 理学秘訣.pp. 379-380、1r)同.p. 380.頭注、1s) 心学奥の棧 下之巻.p. 438、1t)理学秘訣.p. 377、1u)同.p. 389-390.頭注、1v)心学奥の棧 中之巻.p. 421、1w)理学秘訣.p. 386、1x) 解説.石門心学について 七. p. 509.
4)市川安司・遠藤哲夫.荘子(下).新釈漢文大系.第8巻. 明治書院.1975.4a)雜篇 天下 第三十三.pp. 822-823、4b)外篇 知北遊 第二十二.pp. 576-577、 4c)同.pp. 580-581、4d)同.至樂 第十八.pp. 499-501、4e)同.知北遊第二十二.pp. 573-575.
5)渡邊 徹.本邦最初の經驗的心理學者としての鎌田鵬の研究.中興館.1940.5a)第二章 鎌田鵬の氏名および家譜.第一節 氏名.pp. 15-17、5b) 第七章 鵬の心理思想.第二節 心理學一般.第三項「究理緒言」(「心學奥の棧」).pp. 322-333、5c)同.第二項「理學秘訣」.二、内容および構成.p. 308、5d)第五章 鵬の學統.第四節 理學.第三項 朱子の心學と鵬.pp. 222-227、5e) 第七章.第二節.第二項「理學秘訣」.三、經驗的心理學(心の用)― 知識.pp. 310-311、5f) 第五章 .第四節 第三項.p. 219-222 5g)第五章.第二節 自然科學.pp. 167-177、5h)第二章.第四 節 一家.p. 96、第五章.第一節 醫學.p166、5i) 第七章.第二節 第二項.五、心身の關係および心意の成因.pp. 316-317、5j) 第五章 .第四節 第六項.明末耶蘇會士の性學.p. 254.5k)第七章.第二節 第二項 七、世界における人間の地位.p. 318.
6)福永光司.荘子(内篇).中国古典選12.吉川幸次郎 監修.朝日新聞社.1978.6a) 逍遙遊篇 第一.pp.29-30、6b)大宗師篇 第六.pp. 267-269、6c)大宗師篇 第六.pp. 292-294.6d)齊物論篇 第二.p. 58.
7)市川安司.近思録.新釈漢文大系.第37巻.明治書院.1986.7a) 近思録解題.編者.p. 10、7b) 近思錄 卷一 道體.p. 1、7c)同.p. 3.
8)中国宗教思想 2 .岩波講座 東洋思想 第十四巻.岩波書店.1990.8a)池田秀三.Ⅱ中国宗教思想の特質(続).3 存在と理法.4 不易と流行.一 理気二元論における不易と流行.pp. 48-49、8b)同.三 変易する世界.p. 52、8c)松村 巧.同.6有と無.一 先秦思想史における「有」と「無」.pp. 76-79、8d)福永光司.4自と他.2 一と多.四 p.152.8e) 池田秀三.3.1 陰と陽.一 陰陽の基本的性格.pp. 5-9.
9)小野沢精一・福永光司・山井 湧.気の思想.東京大学出版会.1978.9a)山井 湧.第三部 理気哲学における気の概念 総論.二 理および「理の哲学」pp. 360-361、9b)同.第二章 朱熹の思想における気.一 理気論.3理と気.p. 443、9c) 加納喜光.第二部 儒道仏三教交渉における気の概念.第一章.魏晋南北朝の気の概念.第三節 医書に見える気論.p. 290、9d)大島 晃.第三部 理気哲学における気の概念.第一章 道学の形成と気.第二節 邵雍と張載における気の思想.pp. 408-409、9e)山井湧.第三部 総論.一 宋学における気.pp. 357-360.9f)小野沢精一.第一部 原初的生命観と気の概念の成立.第二章 戦国諸子における気.第一節 斉魯の学における気の概念.p. 77、9g)福永光司.第一部 第三章 秦漢期の気の思想.第一節 道家の気論と『淮南子』の気.pp. 127-131、9h)麦屋邦夫.第二部 第一章 第二節 道家・道教における気.p. 268、9i) 第一部 第三章 第一節.pp. 133-146、9j)福井文雅.第二部 第二章 隋唐・五代の気の概念.第一節 儒道仏三教における気.p. 316.
10)三浦国雄.朱子.人類の知的遺産 19.講談社.1979.10a) Ⅰ朱子の思想.2基礎諸概念.理気.pp. 18-19、10b) Ⅲ 朱子の著作.1『朱子語類』抄.五 修養論.窮理.p.298、10c)同.天理.p. 306、 10d)I. 2. pp. 16-18、10e)Ⅲ.1.一 存在論.天地.p. 267、10f)同.p. 272、10g)同.p. 270.
11)ジョゼフ・ニーダム.中国の科学と文明.第3巻 思想史(下).思索社.1991.11a)第16章. 晉・唐間の道家と宋代の新儒家たち.(d)新儒家たち.(3)普通的パターンの研究-氣(物質=エネルギー)と理(組織)の概念.pp. 524-525、11b)同.(2)太極.pp. 508-509、11c)同.(3)普遍的パターンの研究.p. 521、11d)同.pp. 520-521、11e)同.(3). pp. 529-530.
12)福永光司.荘子(外篇・下).中国古典選15.吉川幸次郎 監修.朝日新聞.1978.12a)知北遊篇 第二十二.pp. 186-188、12b)同.p. 201、12c)同.pp. 181-184.
13)ジョン・グリビン、メアリー・グリビン.進化論の進化史.水谷 淳 訳.早川書房.2022.13a) 第Ⅰ部ダーウィン以前.第2章 偽りの夜明け.pp. 55-56、13b)同.p. 73、13c)第3章 時の賜物.p. 70.
16)アリストテレス全集 9.動物運動論 動物進行論 動物発生論.島崎三郎 訳.岩波書店.1969.16a)動物発生論.第2巻 第1章.訳者註(30)p. 346、16b)同.733b, 734a, 734b: pp. 152-154、 16c)同.735a: p. 157、16d) 第1巻第23章731a: p.143、16e)同.第8章.747a26-749a4: pp. 194-199、16f)同.第7章.746b: p. 192-193, 同.訳者注(14), (15), (16), (17), (18). p. 368、16g)動物発生論.第3巻 第11章.762a10-30: p. 237、同.訳者註 (15), (16): p.388 .
18)ジョゼフ・ニーダム.中国の科学と文明.第2巻 思想史(上).思索社.1991.18a)第10章 道家と道教.(b)「道」の道家的観念.pp. 45-46、18b)同.(e)変化、変形、および相対性.p. 98、18c)同.pp. 97-99、18d) 第13章. 中国科学の基本思想.(g)『易經』の体系.(1)吉凶の兆の格言から抽象的概念へ.第14表『易經』の六爻の意味.p. 362、18e)同.(c)陰陽家,騶衍および五 行説の起源と展開.(1)他の民族の元素理論との比較.pp. 285-287、18f)同(1).pp.272-273、18g)同.(d)列挙の順序と象徴的相関関係.(1)列挙の順序とその組み合わせ.p. 297、18h) 第10章 .(c)自然の統一性と自発性. p. 60.
25)ヒッポリュトス.全異端反駁.キリスト教教父著作集 19.大貫 隆 訳.教文館. 2018.25a) 第1巻自然哲学者 クセノファネス 一四. p. 82、25b)同.アナクシマンドロス 六.p. 74.
28)楠山春樹.淮南子(上).新釈漢文大系.第54巻.明治書院.1979. 28a) 巻四 墬形訓 十四. pp. 237-240、28b) 同.五.pp. 214-216、28c)同.十三.pp. 234-237、28d)巻三 天文訓.二十二.p. 192、28e)同.pp. 130-132、28f)同.pp. 167-168、28g)巻一 原 道訓.十三.pp. 62-63.
32)APG牧野植物図鑑Ⅰ.邑田 仁 監修.北隆館.2014.32a)目次.p. 1、裸子植物.マツ目.マツ科.pp. 15-21、32b)被子植物.単子葉類.キジカクシ目.アヤメ科.ハナショウブ.p. 138、32c)同.ショウブ目.ショウブ科.ショウブ.p. 56.32d)ヒノキ目.ヒノキ科.スギ.p. 28.
57)ピータ―・J・ボウラー.進化思想の歴史(上).鈴木善次・横山輝雄・森脇靖子・田中紫枝・柴田和子・斎藤 光・大林雅之 訳.朝日新書335.朝日新聞社.1987.57a) 田中紫枝.6 ダーウィニズムの起源.pp.267-268、57b)八杉龍一.解説 日本の思想史における進化論-ボウラー『進化思想の歴史』の訳書に寄せて. 2. Ⅳ―Ⅴ.
72)佐倉 統.進化論の挑戦.角川書店.1997.72a)第一章 進化と進化論の歴史.2 進化論の歴史.p. 22、72b)同.p. 25.
75)福永光司.荘子(外篇・中).中国古典選14.吉川幸次郎 監修.朝日新聞社.1978.75a)至楽篇.第十八.p. 253、75b)同.pp. 250-253、75c)秋水篇.第十七.pp.168-170、75d)同. pp. 187-190、75e)同.p. 190、75f)至楽篇.第十八.pp. 232-233.
82)ジャック・ロジェ.大博物学者ビュフォン.ベカエール直美訳.工作舎.1992.82a)Ⅲ 長い忍耐を要した『博物誌』.第十九章.種、属、科—新たな分類を目指して.pp. 379-382、82b)同.p. 382、82c)Ⅳ 歴史を視野に入れて.第二三章.歴史と自然.p.479.
87)G. S. カーク, J. E. レイヴン, M. スコフィ-ルド.ソクラテス以前の哲学者たち(第2版).内山勝利・木原志乃・國方英二・三浦 要・丸橋裕 訳.京都大学学術出版会.2011.87a) 内山勝利 訳.第3章 ミレトスのアナクシマンドロス .Ⅶ.動物および人間の発生.pp. 184-186.
88)Benoît de Maillet. Telliamed, ou Entretiens d’un philosophe indien (Éd. 1748). Tome 2. Hachette Livre. BnF. 2013.88a)SIXIE’ME JOURNE’E. pp.133-140、88b)QUATRIE’ME JOURNE’E. p. 54.
92)ヘルダー.人類歴史哲学考(一).嶋田洋一郎 訳.岩波書店.2023.92a)第一部 第二巻.一 われわれの地球という球体は、きわめて多様な存在物を有機組織化するための大きな作業場である.p. 105.92b)第一部 第五巻.一 われわれの地球の被造物界においては一連の上昇する形と諸力が支配している。p. 289.
103)司馬江漢全集 二.春波楼筆記.西洋天地開闢.朝倉治彦・海野一隆・菅野 陽・中山茂・成瀬不二雄・沼田次郎.八坂書房.1993.103a)春波楼筆記.西洋天地開闢.pp. 102-103、103b)独笑妄言.蟻道和尚談義.pp. 12-13、103c)春波楼筆記.pp. 72-73、103d) 春波楼筆記.pp . 87-88.(春波楼筆記.文化八年.1811:未刊行).
104)海老澤有道.南蛮学統の研究.創文社.1958.104a)後篇 南蛮学統の思想的影響.第八章 司馬江漢の人間観・宗教観.Ⅱ造化論.註2.p. 387、104b)同.p .385.
106 )中山 茂.『乾坤弁説』の原著とクラヴィウス.蘭学資料研究会.研究報告.第136号.p. 1.1963(5.18).
107 )デカルト.科学の名著 第Ⅱ期7(17).井上庄七・小林道夫 編集.朝日出版.1988.107a) 井上庄七・水野和久・小林道夫・平松希伊子訳.哲学の原理.第四部 地球について.pp. 194-217.
108 )Buffon. Histoire Naturelle. Tom Premier(I). A Paris, De L’Imprimerie Royale. 1749.108a)Preuves de la Théorie de la Terre. Art. VII. Sur la production des couches ou lits de terre. pp. 229-265、108b)” I. De la formation des Planèts. pp. 149-150、108c)” XVI. Des Volcans des Tremblemens de Terre. pp. 502-535.
109 )司馬江漢 全集 三.朝倉治彦・海野一隆・菅野 陽・中山茂・成瀬不二雄・沼田次郎.八坂書房.1994.109a)和蘭天説.p. 42、109b)天球図・天球全図.大陽真形.pp. 86-87、解題.天球全図.5. p. 359、109c)同.月輪真形.pp. 88-89、解題.同.6. pp. 359-560、109d)天地理譚.p. 291、109e)同.p. 295、109f)和蘭天説.p. 66、109g)同.p. 68、109h)同.p. 69、109i) 同.pp. 72-73、109j)同.p. 70、109k)刻白爾天文図解.小言.p. 218.
110)アリストテレス全集 5.気象論・宇宙論.泉 治典・村治能就 訳.岩波書店.1969.110a) 気象論.第2巻第7章.365a: pp. 86-88、訳者註(1).p. 190、110b)同.第8章.366a, 367b, 368a: pp. 89-97、110c)同.第9章.370a: p101、110d)宇宙論.第4章.395b20-396a: p. 258-259.
111 )Georgii Agricolae. De ortu et causis subterraneorum. Officina Frobeniana. 1558. 111a) pp. 16-32.
Internet Archive. https://archive.org/details/georgiiagricola00agri. Contributor : Smithsonian Libraries. Added date 2017-07-19 18:33:20
112)ジャック・レプチェック.ジェイムズ・ハットン.平野和子 訳.春秋社.2004.112a)第8話 疑問が解けた!.pp. 162-179、112b)プロローグ.pp. 6-10.
113)Athanasii Kircheri. Mundus subterraneus. Liber secundus Thechnicus. Geocosmus, sive De admirando Globi Terreni opificio. Joannem Janssonium. 1665. 113a)CAPUT V. De Corporis Lunaris Natura & EffeԐtibus.p. 62 (Fig. Luna)、113b)CAPUT Ⅵ. De proportione Globi Terræ ad Solem ac Lunam.p. 64 (Fig. Solaris).
Internet Archive. https://archive.org/details/mundussubterrane00unse. Contributor : Roger Wagner. Added date : 2012-02-03 00:57:55.
114)司馬江漢百科事展.塚原 晃・成澤勝嗣・内田啓一.神戸市立博物館・町田市立国際版画美術館.便利堂.1996.114a)第4章 窮理学者の道.天球全図.4-22 天球全図 太陽真形図.p. 142、4-24 天球全図 月輪真形図.p. 143.
115)Athanasius Kircherus. d’ONDER-AARDSE WEERELD. D’Erfgenamen van wylen Joannes Janssonius van Waasberge. 1682.115a) II. Boek, Van het Werkstuk des Aardkloots. After p. 70. Fig. TYPUS CORPORIS LUNARIS PANSELINI, UNA CUM MACULIS, FACULIS MONIBUS., ” After p. 72. Fig. SOLARIS、115b) IV. Boek, Beschryvende het Vuur. After p. 210. Fig. Qvo EXPRIMITUR, AQUARUM., ”After p. 218. Fig. PYROPHY LACIORUM、115c)” Het Ⅵ. De Vuur-brakende Bergen, die in het buitenste Oppervlak des Aardrijks te sien zijn, toonen genoegsaam dat de Aarde vol Vuur is. p. 219.
https://books.google.co.jp/books?id=Wj5FAAAAcAAJ&hl=nl&source=gbs_navlinks_s. Oorspronkelijk uit : Universiteit Gent. Gedigitaliseerd : 7 dec 2010.
116)乾坤辨説.文明源流叢書.(本論)澤野忠庵 編述・(辨説)向井玄松 議.(通辞)西 吉兵衛.国書刊行会編.1914(大正3年).参考:文明源流叢書 第二(中巻).名著刊行会.1969.116a)亨巻(イ上巻の二)第十四 地震之事.pp. 38-39、116b)第十七 海水鹹味之事.p. 42、116c)第二十二 風大の中に生ずる物の事.p. 48、第二十三 下部の風中に生ずる物の事.pp. 48-53、116d) 元巻(イ上巻の一).第三 萬物は四大和合之物なる事.p.16、116e)同.第二 地水風火互連次第幷相克相生の事.p15、116f)元巻(イ上巻の一)序.向井玄松.四國學例.pp. 6-7、116g ) 亨巻(イ上巻の二)第二十一 風大吹氣之事.p. 48.
*参考:平岡隆二.『乾坤弁説』諸写本の研究.長崎歴史文化博物館研究紀要.1.pp. 51-63.2006.
117)Buffon. Histoire Naturelle, Générale et Particulière. Supplémnt. Tom Cinquième (Ⅴ). A Paris, De L’Imprimerie Royale. 1778.117a)Additions à l’article des Tremblemens de Terre & des Volcans. Ⅰ. Sur les Tremblemens de Terre. pp. 382-386.
118)富永仲基・山片蟠桃.日本思想体系43.水田紀久・有坂隆道 校注者.岩波書店.1973.118a) 有坂隆道 校注.藪内 清・海野一隆・水田紀久 注.山片蟠桃.夢ノ代 .巻之二.地理第二.p. 259、118b)同.天文第一.p. 222、118c)同.頭注.p. 185、118d)同.p. 187.118e)夢之代 跋.p. 616.
119)朱子語類.朱子學大系 第6巻.諸橋轍次・安岡正篤 監修.明徳出版社.1981.119a)佐藤 仁.朱子語類(抄).理気(巻一・二)・頭註.p. 27、119b)同.p. 21.
120)今井宇三郎・堀池信夫・間嶋潤一.易経 下.新釈漢文大系.第63巻. 明治書院.2008.120a)繫辭下傳.p. 1627-1628.
121)白虎通(四巻附校補遺.闕文).巻四上.嫁娶.p. 9.和刻本漢籍古書拓本朝鮮本書道碑帖.1923?
122)中井宗太郎.司馬江漢.アトリヱ社.1942.122a)和蘭天説.p. 36、122b)同.pp. 46-48、122c)同.p. 30.
123)インド仏教 2 .岩波講座 東洋思想 第九巻.岩波書店.1988.123a)森 祖道.Ⅱ インド仏教思想の展開(続).7 南方仏教思想.2 南伝アビダルマ思想の体系.二 物質論.1 物質の種類.p .74.
124)遠藤哲夫.管子 中.新釈漢文大系 43.明治書院.1991.124a) 第十四.水地第三十九(短語十三).pp. 730-733、124b)同. pp. 724-725.
125)阿部吉雄・山本敏夫・市川安司・遠藤哲夫.老子・荘子(上).新釈漢文大系.第7巻.明治書院.1975. 125a) 老子道經上.體道第一.pp. 11-12、125b)同. 象元第二十五.p. 52、125c) 老子道經下.去用第四十.p. 76、125d) 同.道化第四十二.pp. 78-79.125e)市川安司.内篇 斉物論第二.pp. 178-179.
126)黒木賢一.東洋における気の思想.大阪経大論集.56(6).2006.126a)「陰陽五行」の世界観.1陰陽論.p. 93.
127)三浦国雄.張載太虚説前史.集刊東洋学 巻 50.p. 55-75.東北大学 中国文史哲研究会.1983.127a)p67-68、127b)pp. 63-64、127c)p. 59、127d)p. 72、127e)p. 56 .
128)山際明利.張載思想研究.北海道大学出版会.2024.128a)第二部 張載の思想.第一章 「太虚卽氣」— 存在論、本體論.一 張載の生滅論.pp. 54-55、128b)同.二 張載の本體論.p. 60、第三部 宗明理學の中の關學.第三章.五 朱熹の太極解釋. pp. 212-213、同.本章の結び.〔注〕(3).p. 225、128c)第二部.第一章.一.p. 51.
129)楠山春樹.淮南子.中国古典新書.明徳出版社.1971.129 a)本文 三、天文篇(1)天地の始まり.p . 90、129b)同.pp. 91-92.
130)三枝博音 編.三浦梅園集.岩波文庫.1953.130a)多賀墨郷君にこたふる書.p. 18.
131)福永光司.荘子(外篇・上).中国古典選13.吉川幸次郎 監修.朝日新聞.1978.131a)天地篇.pp. 194-195.
132)更科 功.世界一シンプルな進化論講義.講談社.2025.132a)第5講義 さまざまな生命現象と進化論.全生物の「共通祖先」は「地球最初の生物」でなかったかもしれない.pp. 203-205.
133)細胞工学.35(2).秀潤社.2016.133a)赤沼哲史.全生物の最後の共通祖先コモノート.pp. 124-128.
134)Bonnet. Collection Complette des Œuvres de Charles Bonnet. Tom. Premier (Ⅰ). D’Historire Naturelle et de Philosophie de Charles Bonnet. A Neuchatel, De l’Imprimerie de Samuel FAUCHE, Libraire du ROI. 1778.134a)Préface. p. xxxⅢ. IDÉE D’UNE ÉCHELLE. Des etres naturels. Table.
135)ヘルデル.歴史哲學.田中萃一郎・川合貞一.第一書房.1932.135a)第一編.第五巻.一 我が地球上の生物に於いては形式と氣力とが向上的に序列を爲して居る.p. 311.
136)森 三樹三郎.老子・荘子.人類の知的遺産5.講談社.1978.136a)Ⅲ 老子・荘子の書.4 『老子』の訳文と解説.p. 124、 136b)Ⅰ 老荘の思想.2 荘子の思想.二.人間の運命の肯定 — 死生を斉しくす.p. 61.
137)池田和久.淮南子.講談社.2012.137a)巻第一 原道.7 一と道の関係について.p. 65.
138)中村 昇.ホワイトヘッドの哲学.講談社.2007.138a)第2章 入門篇― ホワイトヘッド哲学そのもの.11 神と世界.pp. 137-138、138b)第1章 入門以前―ホワイトヘッド哲学の見取り図.9 いきいきとした自然.pp. 64-67.
139)新日本古典文学大系99.植谷 元・水田紀久・日野龍夫 校注.岩波書店.2000.139a)植谷 元.仁斎日札.(64).p. 28、原文(64).p. 457.
140)八杉龍一.生命論と進化思想.岩波書店.1984.140a)第二部 進化思想の発展.第六章 進化概念の成立について.2 鎌田柳泓の進化観念.pp. 103-104.
141)John and Mary Gribbin. On the origin of evolution. William Collins. 2020. 141a)Part One: Ancient Times. 2. A False Dawn. p. 47.
142)ビュフォン著.自然の諸時期.叢書・ウニベルシタス 456.菅谷 暁.法政大学出版局.142a)解説.五 時間 (5). p. 405、142b)pp. 404-405.
143)Buffon. Histoire Naturelle, Générale et Particulière, servant de suite á la Théorie de la Terre, & de préliminaire à l’histoire des Végétaux. Supplément. Tom Second (Ⅱ). A Paris, De L’Imprimerie Royale. 1778.143a)Partie Hypothétique. Premier Mémoire. Recherches sur le refroidissement de la Terre & des Planètes. p. 404.
144)Jacobo Usserio. Annales Vesteris Testamenti, A Prima Mundi Origine Deducti. Una Cum Rerum Asiaticarum Et Aegyptiacarum Chronico. (1650). p. 1 (p. 11). Kessinger Publishing. 2009.
145)R. M. ウッド.地球の科学史.谷本 勉 訳.朝倉書店.2008.145a)1.新石器時代.1.2地質学の心理学.p. 9.
146)森田健司.鎌田柳泓の思想における心学的基盤 —『心学五則』を再読する—.大阪学院大学.経済論集.27(1・2).51-77.2013.146a)1.江戸思想の先進性.p. 53.
147)ダーウヰン.種の起源.序論. pp. 3-4.松平道夫 譯.太陽堂.1926(大正15年).
148)木村資生.生物進化を考える.岩波書店.1988.148a)第5章.1 ダーウィンによる自然淘汰の考え.pp. 122-123.
149)Charles Darwin, M. A. On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life. John Murray. 1859. 149a)On the origin of species. Introduction. p. 3.(第1~5版までのタイトルは「On the Origin of Species」)
Internet Archive. https://archive.org/details/darwin-online_1859_Origin_F373/page/n17/mode/2up. Contributor : Darwin Online. Addeddate : 2015-11-24 20:30:52.
150)現代進化論の展開.「科学」編集部.岩波書店.1982.150a)Stephen Jay Gould. 1 進化論とは何か.ダーウィニズムと進化論の発展Ⅰ.p. 27.・目次にStephen G. GOULDと誤記
151)宮田 隆.分子からみた生物進化.講談社.2014.151a)第1章.ダーウィンと近代進化学の幕開け.種はどのように生まれるか.pp. 26-33.
152)大島長造・北川 修・深民玲之・柳澤嘉一郎.遺伝と変異.生物学教育講座4.大島長造編.東海大学出版会.1981.152a)北川 修.3.集団の遺伝.3・9 生物進化.3・9・1進化学説の発展.(2)ダーウィン.p. 130.
153)岩波 生物学辞典.第5版第1刷.巌佐 庸・岩倉 滋・斎藤成也・塚家裕一 編集.岩波書店.2013年.153a) 進化.pp. 687-688.
154)岩波 生物学辞典.第1版第1刷.山田常雄・前川文夫・江上不二夫・八杉竜一 編集.岩波書店.1960年3月10日.154a)シンカ 進化.pp. 493-494.154b)進化論
155)秋田孝季・和田吉次・菅江真澄・和田末吉.東日流六郡誌絵巻.山上笙介 編集・構成.津軽書房.1986.155a)東日流六郡誌大要 一の巻.宇宙創誕のこと.pp. 107-108、155b)同.万物創誕のこと.pp. 108-109.
156)藤本光幸.和田家資料2.丑寅日本記・丑寅日本紀・日之本史探証.北方新社.156a)和田長三郎.丑寅日本紀 第九.万物生々進化之事.pp. 223-224.